|
�͂��߂܂��āE�E�E�T�b�J�[�@�g���Z���R�[�`�̂m�`�a�n�ł��B |
|
�@�i�͂��߂ĖK�₷����͂��̃y�[�W����ǂ�łˁB��x�ڈȍ~�͂��̂���������ˁj
�@
�͂��߂܂��āE�E�E�m�`�a�n�ł��B
�@
�@ ���N�T�b�J�[�`�[���̌����R�[�`�ł��B
�@�n��̃g���Z���i�g���[�j���O�Z���^�[�̗��ł��B�j�̃R�[�`���S�����Ă��܂��B
�@�T�b�J�[����D���ł��B�T�b�J�[�������鏭�N����D���ł��B �T�b�J�[���N�E�����ƁA�T�|�[�g���邨������A���ꂳ��ƃR�[�`�h���܂��B
�@���ɂ͒j�̎q���Q�l���܂��B��̎q�͂����A���Z���ɂȂ�܂����B �T�b�J�[���N�����e�̗���A�ی�҂�ی�҉�̗�����o�����Ă��܂��B
�@�����āA�R�[�`�A�`�[���^�c�A�g���Z�������ȂǁA���N�T�b�J�[�Ɋւ�銈���Ɍg����Ă��܂��B ���̂V�N�Ԃ́A�N�ɂP�Q�O���ȏ�O�����h�ɗ������𑱂��Ă��܂��B����ɗ��ĂȂ���T�b�J�[�R�[�`�ł͂Ȃ��I�����b�g�[�ł��B
�@ �Ȃ�āA���́A�q���������疈��p���[��������Ă����ł���B�����瑱���Ă������ł��ˁB
�@�͂��߂͎����u��������R�[�`�v�ł����B ���w�����瑐�T�b�J�[���n�߂āA���w�A���Z�A��w�A�Љ�l�ƃT�b�J�[���y����ł��܂������A�T�b�J�[������v���[���[�Ǝw������R�[�`�͂P�W�O�x�ʐ��E�ł��邱�Ƃ�m��̂Ɏ��Ԃ�������܂����ˁB
�@�i�e�`�@���{�T�b�J�[����ł́A���F���C�Z���X���x��݂��Ă��܂��B
�@���N�T�b�J�[�ł���c�����C�Z���X���L�҂��`�[���ɂP�����Ȃ��ƌ�����ɏo�ꂷ�邱�Ƃ��ł��܂���B ���͂c�����擾���A���̌�A���̏�̃��C�Z���X�ł���b�����C�Z���X���擾���܂����B ���̑��A�L�b�Y���[�_�[�t�U�i�c�t���j�A�t�W�i���w�Q�N���ȉ��j�A�t�P�O�i���w�S�N���ȉ��j�̎��i���擾���܂����B
�@ ���̂悤�ɁA�u�T�b�J�[�w���v�ɂ��ĕ����Ă����ƁA�v���[���鎖�Ǝw�����鎖�̈Ⴂ�ɋC���t���͂��߂܂����B
�@ �u��������R�[�`�v����ɂ́A�u���ŏo���Ȃ��낤�H�v�ƕs�v�c�Ɏv���Ă��������A�u�o���Ȃ��ē��R�Ȃv�Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B
�@ �����āA�u�o����悤�ɂȂ邽�߂ɂ͂ǂ�����������H�v ����ɂ��āA�l���āA�w�����āA���͂��āA�܂��l���āA�w�����āE�E���J��Ԃ��Ă��܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���N�T�b�J�[�R�[�`�@NABO
�@�@�@�@�@�@�m�`�a�n����̃��[���}�K�W���o�^�͂����炩��E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Ǘ��l�̂₶�܂�������E���܂��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�e�q�̂��߂̃T�b�J�[�R�[�`���O�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://jr-soccer-coaching.naotech.info/
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�����}�K�L���̍ŐV�łɌf�ڂ́u���T�̃g���[�j���O�v����̋L���́E�E�E�������N���b�N�@
�@ |
|
|
|
|
|
�����Q�P�@���N�����̂����܂����ƃ}�C���h�͐e���e������Ƃ������� |
|
�@�@�@�@�@�Q�O�O�X�C�W�C�P�R
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�@����A��33��S���{���N�T�b�J�[����܂����B�D���͖��É��O�����p�XU�P�Q�ł����B�O����ŏ��D���ŗ܂������������č��N�̃`�[���̏o���͑f���炵�����̂ł����B
�@�P�����E���h���i�r���b�W�ɏo�����Ċϐ킵�Ă��܂����B
�@���N�T�b�J�[�����N�g�����h������܂��B �ȑO�͂S�o�b�N�ŃX�C�[�p�[��u�����`�[��������܂������A�ŋ߂͂��̂悤�ȃ`�[���͌��Ȃ��Ȃ�܂����B�S�o�b�N�ł��Z���^�[���Q���ŗ��T�C�h�̑I��͐ϋɓI�ɍU�ߏオ��܂��B
�@J���[�O���\�`�[���̐킢���̏k���ł̂悤�Ȃ��̂ł��B �e�s���{���̑�\�ł�����A���͂�����`�[������ł��B�o�ꂷ��I��݂͂�ȏ��ł��B
�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@���ł����A��������������ƌ������͂���ɏ��ȑI�肪����Ƃ������ɂȂ�܂��B���w���ł�����A���Ƃ͌����Ă��~�X�����܂��B�~�X�̏��Ȃ��`�[���͎��_�����Ȃ��A�U�������Ă��鎞�Ԃ������̂Ō��ʂƂ��ē��_���܂��B
�@�i���[�O�̉����`�[���̂����A�S�`�[���������g�[�i�����g�ɏo�ꂵ�܂����B�O�����p�X�A�t�����^�[���A�R���T�h�[���A�A���f�B�[�W���ł��B�O�����p�X�ƃt�����^�[���ƃA���f�B�[�W���͓����R�ɓ����Ă����̂łԂ������ɂȂ��Ă��܂��܂����B�R���T�h�[�����R�ʂɓ��������͕����i������\�j�ɕ����Ă��܂��܂����B
�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�i���[�O�̉����`�[���������̂́A�Z���N�V�������s���A����Ƀv���R�[�`�̎w������ƂƂ��ɁA��������g�b�v�`�[����_���Ƃ����������`�x�[�V������������̂ŁA�ނ炪�����̓��{��\�����o�[�ɂ�����x���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�����A�S���{���N�T�b�J�[�������o���̂����\�I������܂��B
�@���w���ł��ꂮ�炢�ł���̂�����A���w���ɂȂ����炳��ɏ��ɋ����Ȃ邾�낤�B
�@�����Ă��͂����v���܂��B�������A�����s���Ȃ��̂��琬�N��̃T�b�J�[�̓���ł��B
�@���w�̃T�b�J�[�܂�W���j�A���[�X�A���Z�T�b�J�[�܂胆�[�X�Ƃ����e�J�e�S���[�ɂ����āA�L�т�I��A�L�т��~�܂�I�肪����Ă���킯�ł��B
�@�܂��A�S���{�̓s���{�����Őɔs�����`�[���̑I��̒��ł��A���w���ɂȂ�����}�ɐL�т��A�܂艻����Ƃ����\����剻������Ƃ����\���������܂����A�ǂ̔N��ŐL�т邩�킩��܂���B
�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@���������ɂ�����邠�܂�A�ڐ�̏��s�ɂ�����邠�܂�A�q�������̃T�b�J�[�͂܂��n�܂�������Ƃ������ɋC�t�����A���Z���̃��[�X�N��ł̊�����ڎw���ăg���[�j���O���郂�`�x�[�V�������ێ��ł��Ȃ����ʁA�T�b�J�[�������ɂȂ�~�߂Ă��܂��Ă̓m�[�`�����X�ł��B
�@���L�т�낤�B�T�b�J�[���N�̐e���q��Ă����߂ĂȂ�A�T�b�J�[���N���������������߂Ăł��B�ǂ��ڂ��Ă����悢�̂��Y�ނƂ���ł��B
�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�}�C���h�̎������ŏ��������܂�Ƃ����Ă��悢�ƌ����܂��B
�@�T�b�J�[���y�����Ɗ��������ɂɊ������肷��̂͌��ǂ͖{�l�̐S�ł��B
�@�S�̎��������������肵�Ă���A�����o�[���O���ꂽ��A�����ő�~�X�����Ă��A���炸�A�߂����ɗ����オ��ł��傤�B
�@�������x����̂͏��N���ɂ����ẮA�e��R�[�`�̑��݂��傫�����̂ł��B�q������������������B�e�͎���o�������C������}���Ȃ���Ȃ�܂���B�����q���Ɏ��݂��Ă��ẮA�����ł���͂��͂���܂���B�܂��A�~�X���������ӂ߂邱�Ƃ��A�q���ɂ悢�e��������Ƃ͌����܂���B
�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�e�͎q�����T�|�[�g���Ă����邱�ƁB
�@�ړ��╨�i�̍w���ȂǁA�q�������K�⎎�����ł�������T�|�[�g���鎖�ɓO���鎖����{�ƍl���܂��B �q���������Ȃ��Ȃ���B���Ȃ����A�X�^�����ɓ���Ȃ����͂����Ɖ䖝���Ă���̂ł��B�����������́A�e���K�}���ł��B
�@�u�撣�肪����Ȃ��v�Ƃ������t�̓L�c�C���̂�����܂��B�q�����������������邱�ƁB����͂P���ł�����̂ł͂���܂���B���͂��傤�ljċx�݂ł��ˁB�q�������������ōl���A���f���A�s������Ƃ������̓s�b�`�̒������ň�܂����̂ł͂���܂���B�ƒ�̐����A�Љ�̒��ł����ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@���킢���q�ɂ͗���������B�Ƃ́A��J����������A�~�X���o�������鎖�ƍl���܂��B���肵�āA�q�����Ԃ���ׂ��ǂ��J����菜������A�~�X�����Ȃ��悤�ɂ��鎖�Ŏq�������́A���z���邽���܂����S�����o���������܂��B
�@�}�C���h�̎����������w�������̍���ɂ������Ă���B�����ɐe�̑��݂���A�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���N�T�b�J�[�R�[�`�@NABO
�@�@�@�@�@�@�m�`�a�n����̃��[���}�K�W���o�^�͂����炩��E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Ǘ��l�̂₶�܂�������E���܂��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�e�q�̂��߂̃T�b�J�[�R�[�`���O�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://jr-soccer-coaching.naotech.info/
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�����}�K�L���̍ŐV�łɌf�ڂ́u���T�̃g���[�j���O�v����̋L���́E�E�E�������N���b�N�@ |
|
|
|
|
�����P�X�@�@�@�U�N���O�̃r�f�I�œy���Z�킪����Ă������Ɠ������Ƃ��e���r����ł͕��Ԏ��������Ă��܂��B |
|
�@�Q�O�O�X�D�T�D�P�V
�@
 �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�����E��ڎw�����߂ɕK�v�ȃt�B�W�J���Ƃ�
�@�y�����̓{�[�����t�e�B���O�Ő��E�I�ɗL���ł����A���͓y��������߂��Ō���ƁA���̃}�b�`���Ԃ�ɋ����Ǝv���܂��B �ł��׃}�b�`���ł��S���}�b�`���ł��Ȃ��A�T�b�J�[�}�b�`���ƌ����悢�̂ł��傤���B
�@�����̐��E�ł́u�Z�͗͂̒��ɂ���v�Ƃ������t������܂��B�ؗ�ȋZ�������Ă��Ă��A�p���[������Ȃ��Ƒ����|�����Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��B
�@ �y������́A�P�P���d�����Ă��܂��B���t�e�B���O��t�F�C���g�̖{�𑽐��o�ł��Ă��܂��B
�@�Z�̂ЂƂЂƂɂ����������Ă��܂��B����́A��������킷�Ƃ������ł��B
�@�y������̃��t�e�B���O�V���[�������ɂȂ��������吨����Ǝv���܂����A�p����Ⴍ������A��������A���Ԃ��ɂȂ����肵�Ȃ�����{�[���R���g���[��������܂���B
�@ ����́A���ɂȂ��ė��s���Ă���u�̊��g���[�j���O�v�̂������Ȃ̂ł��B���̃u���O����}�K�ł��z�q���l���̃g���[�j���ODVD���Љ�Ă��܂����A���̂R���ڂɂ͑̊��g���[�j���O��������������Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�y�����́A�̊��g���[�j���O�Ƃ������t��R�A�g���[�j���O��C���i�[�}�b�X���Ƃ������t�����s����܂�����A���̂悤�ȃg���[�j���O���������Ă��Ȃ����������ł��B
�@�X�N���b�g��r���ĕ����╠�Ƃ����x�[�V�b�N�Ȃ��̂ł����A����𐔕S�����Ȃ��Ƃ����y�����ł����A�r��r�̋ؓ������邱�Ƃ��ړI�łȂ��A�̊����Ԃ�Ȃ��悤�Ȑg�̂��ێ����邱�Ƃ��ړI�Ȃ̂ł��傤�B
�@�ڂ����͊�Ɣ閧�Ȃ̂ŁA�V���̓y������ɒ��ڕ����Ă݂Ă��������B����܂��Ȃ��悤�ɂˁi�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@ ���{�T�b�J�[����ł��A���N�O����u�̊��v�u�R�A�v�̃g���[�j���O���i�V�����g���Z���œ������͂��߂܂����B
�@����܂ł́A�{�[���R���g���[����A�W���e�B�i�X�e�b�v���[�N�j�����������̂ł����A���{��\�̍��Z�����x�����C�O�Ńt�B�W�J�����S���ʗp���Ȃ����Ɋ�@�����������̂ł��傤�B
�@���݂́A���w���ɂ��̊��g���[�j���O�𐄏����Ă��܂��B���w���⒆�w���͔���i�K������ؓ��g���[�j���O������Ɣw���L�тȂ��Ȃ�̂ł́H�����S�z������������Ǝv���܂��B �����w���ŁA�E�G�C�g���g�����g���[�j���O�͔�����ׂ��ł��B�܂�A�S�A���C��_���x����o�[�x���̂悤�ɁA�����̑̂̏d���ȊO�̃��m���g�����g���[�j���O�͊߂�Ԑڎ��ӂ̋ؓ������B���Ă��Ȃ������w���ɂ͌����܂���B
�@�������A�����̑̏d�𗘗p����g���[�j���O�͑S�g�^���ł���ǂ�ǂ�ׂ��ł��Ȃ��Ɣ��甭�B�ʂł̓}�C�i�X�ɂȂ�ƍl���܂��B �ؓ��͎g��Ȃ��Ɣ��炵�܂���B�܂�ׂ�Ȃ��g�����ƂŔ��炵�Ă����܂��B�t�オ�肪�ł��܂����B���_���Ă���܂œo��܂����B�r�̗͂łȂ��A�S�g�^���ł��B����̓T�b�J�[���ꏏ�ł���B
�@�T�b�J�[����������b����悢�̂ł͂���܂���B ���t�e�B���O��h���u���A�p�X�A�t�F�C���g���g�ɂ��Ă����Ȃ��Ƃ���������A�̊��̃g���[�j���O������ƃX�e�b�v�A�b�v���鎖���ł��܂��B����ɁA�����Œʗp����悤�ɂȂ�܂��B�P�P�ŕ����Ȃ��Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@ ���{��\�̕��ϐg���͂ǂꂭ�炢�ł��傤���B���{�l�͔w���������ƌ����܂����A���L�V�R��\���A���[���`����\���������̂ł��B�iGK���܂߂āj �������A���ϑ̏d�̓��L�V�R��A���[���`���ɕ����Ă��܂��B
�@����͍׃}�b�`���������Ƃ������ʂɂȂ�܂����A�T�b�J�[�Ƃ����i���Z�̗v�f�������X�|�[�c�ł͑̏d�������ăX�s�[�h�������������L���ł��B �ӊO�Ɏv��ꂽ��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���{�T�b�J�[����ł͂�����t�B�W�J���g���[�j���O�Ɖh�{�ʂŋ������Ă������ƍl���Ă���悤�ł����A�Q�O�Έȏ��A��\��ڎw���悤�ȔN�ォ�炤��ׂ̃t�B�W�J��������̂ł͂Ȃ��A�����w������c�ƂȂ�̊���b���Ă������Ƃ������ւȂ���Ǝv���܂��B
�@�y���������E��n������Ă��A�����ȑ̂Œʗp���Ă����̂́u�Z�ƃt�B�W�J���v�̗Z���Ƃ����挩�̖�������������ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@ ���炽�߂āA�y�����̐�i����m��ƂƂ��ɁA�����钘����r�f�I�ADVD���J��Ԃ��Č�����X�ł��B�U�N���O�̃r�f�I�œy���Z�킪����Ă������Ɠ������Ƃ��e���r����ł͕��Ԏ�������Ă��܂��B
�@�T�b�J�[�ɂ͋��ȏ��ɂȂ����_�⌾�t�ŕ\���Ȃ����̂���������܂��B���ꂩ����y�����̓����Ɠ��{�T�b�J�[�̓�������ڂ������܂���B
�@�@���ӌ��͎��̊Ǘ��u���O�@http://jr-soccer-coaching.naotech.info/�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[��nabo@naotech.info�܂łǂ����B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə����Ċ����l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w���ɏ]�������������B �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə����Ċ����l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w���ɏ]�������������B |
|
|
|
|
�����P�V�@�g���Z���I���I������Ċ����邱�ƁE�E�E�B |
|
�@�Q�O�O�X�D�R�D�P�S
�@�g���Z���I���I������Ċ����邱�ƁE�E�E�B
�@����A���̃g���Z���I���I��̏����K�����܂����B���w���̂t�P�O�N���X�ł����A�S������t�P�P�܂�T�N���ɂȂ�܂��B
�@�T�N���Ƃ����A�S������n�܂�S���{���N�T�b�J�[���ł��x���`�����X�^�����ɓ���q�����܂��̂ŁA���N�T�b�J�[�Ƃ��Ă͂t�P�O�̂��̎����̓`�[����p���ӎ��ł���悤�ɂȂ�K�v������܂��B
�@ ���K��ŋC�ɂȂ�����������������܂����A���̒n���q�����������̓�����������܂���B�������A�s�ΐ��̂��鎖�Ȃ̂ŎQ�l�܂łɏ����Ă݂܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@ �i�P�j����ɂ��́I���悤�Ȃ�I
�@���K�Ɍ��ꂽ�u�Ԃ���u����ɂ��́I�v�Ǝq���������甭����悤�Ȉ��A���~�����ł��ˁB
�@����͂ǂ��̃g���Z���A�ǂ̎Љ�ł�������O�̎��ł����u�������v�͑�ł��B���_�_�������Ă���̂ł͂Ȃ��A�s�V�̎��������Ă���̂ł͂Ȃ��A�W�c���������邽�߂Ɉ��A����n�܂��Ĉ��A�ŏI���Ƃ������͓�����O�ł��B
�@���A�̓R�~���j�P�[�V�����̂ЂƂł���A���C�Ȉ��A���ł���Ɓu�R�~���j�P�[�V�����c�[���v�̎g���������܂��Ƃ�����ۂ������܂��B
�@�g���Z�������łȂ��A�`�[�������ł��O�ꂳ��Ă��܂����B�v���[�ɊW�Ȃ��Ǝv���Ă��낻���ɂ��Ă��܂��B
�@�����̎q�͂��ƂȂ�������E�E�E�Ƃ������R�͗��R�ɂȂ�܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�i�Q�j�����Ɗ����ɂ���͂�
�@�g���Z���őI�����ꂽ���Ԃ��W�܂��ʂł�����A�ْ�����ȂƂ������������ł��傤�B
�@�������A��l�������Ă����瑹�����܂��B
�@�����ɔ������A�����ɍs�����A�����Ƀv���[����B
�@�~�X������Ă��܂��B�Ԉ�������������Ēp���������v�����������Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B
�@�T�b�J�[�����钇�Ԃ̑O�Ń~�X���鎖�͂��݂��l�ł��B�p���������v�����������Ȃ��Ƃ����C���������݂��l�ł��B
�@�T�b�J�[�����ɗ��Ă���̂�����A�W��������U�܂ŁA�����ɍs�����ė~�����Ǝv���܂��B���܂�������Ƃ����l�����͂V�O�p�[�Z���g�ł��B��̂R�O���ȏ�͊��������K�v�ł��B
�@�`�[���ł������悤�Ȏ��������܂��B�~�[�e�B���O�Ŕ�������q�����������I��ł͂���܂��B�~�[�e�B���O�ŕ��Ԏ��ɑO�ɂłĂ���q�ƌ��̕��ɂ���q�͂��������ł͂���܂��B
�@�g���̍��őO�ɏo���Ȃ��̂Ȃ�A�R�[�`�͎q�����������点��ׂ��ł��B
�@�������Ȃ��q�ɔ�������悤�Ɏd������ׂ��ł��B�������̓v���[�����łȂ��A�I�t�U�s�b�`�ł��\���ł���悤�ɂȂ�ƁA�I���U�s�b�`�ł̃v���[�������Ă���Ǝv���܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@
�@�i�R�j�T�b�J�[�����Ă��܂���
�@�T�b�J�[�����鎖�ƃ{�[�����R�鎖�͎��͈Ⴄ�̂ł��B
�@�ŋ߂́A�t���[�X�^�C���[�Ƃ����W���������h�����Ă��āA�T�b�J�[�{�[�����g���ă��t�e�B���O��p�t�H�[�}���X�̋Z�p�������l�X�������Ȃ��Ă��Ă��܂��B
�@�t���[�X�^�C���[�̓G�́A���q����̊��҂⍂�x�ȋZ�p�̕ǂł��ˁB���K����ʂ����[�łȂ��ł��B����ɂU���Ԃ��炢�͗��K���Ă��܂��B�ЂƂ̋Z��g�ɂ���̂ɉ����������邱�Ƃ����邻���ł��B�l�Ɍ�����Z�p�ł�����A����͂���ł悢�ł��傤�B�{�[���t�B�[�����O�����߂�Ƃ��������������߂�u�߂����t�@���^�W�X�^�v�ł͏d�v�����Ă��܂��B
�@�y����������t�e�B���O����{���ɍL�߂Ă���1�l�ł����A�ނ͎��_������܂��B�@�u�T�b�J�[�̎����Ɏg���郊�t�e�B���O�̃e�N�j�b�N�ɂ�������Ă����ł���v�����T�N���O���炻�̂悤�Ȏ������ɂ��Ă��܂����B
�@�t�������đ��̗��Ń{�[�����������͑f���炵���Z�p�ł����A�T�b�J�[�Ɏg����X�L���Ƃ͉����ʒu�ɂ���ł��傤�B�y������͂��邯�ǂ��Ȃ��e�N�����邵�A�����Ȃ��e�N������Ƃ����Ă��܂��B��������̃v���[���[�Ȃ�ł��ˁB ���̋L����ǂ�ł��鑽���̕��X�͂��q����Ƀt���[�X�^�C���[�ɂȂ��ė~�����Ǝv���Ă���l�����A�u�T�b�J�[����肭�Ȃ��ė~�����v�u�����Ŋ��Ăق����v�u�����ɏo�āA�����Ăق����v�Ǝv���Ă���l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���t�e�B���O�͑�ł����A�T�b�J�[�����邽�߂̂ЂƂ̕��@���Ǝv���Ă��܂��B�T�b�J�[������Ƃ��������V���v���ɍl���Ă��������B�S�[����D���A�S�[����D���Ȃ��A�{�[����D���A�{�[����D���Ȃ��B�܂�A�{�[���ƃS�[���̒D�������ł��B�S�[������Ώ����A�S�[�������Ε����Ȃ̂ł��B
�@ ���t�e�B���O�̏��Ȏq�����܂��B�������A�Q�[���ɂȂ�ƃ{�[���ւ̎����S�ƃS�[���ւ̈ӗ~�����������Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B���̂悤�Ȏq�́A�{�[�������͏��ł����A�T�b�J�[�����Ă��Ȃ��̂ł��B���t�e�B���O���K�������Ԃ����Ă���ł��傤�B����́A�N�ɂ����������Ȃ��Ƃ����C��������ɂ��邱�Ƃ͂킩��܂��B���̕����������̋C�������A�v���[�ɏo���ė~�����̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@
�@�i�S�j�U���I�ɂȂ�Ǝ�������܂��Ȃ�B
�@���N�T�b�J�[�ł́A�U���𒆐S�ɃX�L����O���[�v��p��g�ɂ��ė~�����Ǝv���܂��B�f�t�F���X��g�D�I�ɍs�����Ƃ́A���[����g�ɂ��鎖�⒇�Ԃǂ����̓��ꂵ���ӎ����K�v�Ȃ̂ŁA������x�T�b�J�[�Ƃ����Q�[���Ɋ���āA�X�L����Ȃ��Ɠ���ƍl���܂��B
�@������K�����ʂ��Ƃ������ł͂Ȃ��A�g�D�܂�A�`�[���Ƃ��Ă̎�����K������Ȃ�A�U�����K�Ɏ��Ԃ������ׂ����Ƃ����l�����ł��B�U���̂P�P�̏�ʂ��������Ƃ��܂��B
�@�������̂��܂ł��P�P�̂܂ܐ��b�o���Ă��܂����͂��肦�܂���B�U�������ւ�邩�A��������ւ�邩�A���I�D�ʂ���낤�Ǝ��肪�����܂��B
�@�����ő�Ȏ��́A�U���ɐl����������Ƃ����ӎ��������ė~�����Ƃ������ł��B
�{�[���������āA���ŃT�|�[�g���邾���ł͍U���I�Ƃ͌����܂���B
�@�{�[����ǂ��z���I��A�T�|�[�g��ǂ��z���I��A�܂�A�{�[���Ƒ���S�[���̊ԂɍU������l�����肱�ނ��Ƃ��u�U���v�Ȃ̂ł��B�~�X���邩������܂���B�~�X������߂邱�Ƃ�������������ł��B���̂悤�ȃQ�[�����`�[�����ōs���Ă���A����ɐ�ւ�����u�ԂɁu�߂�v�������Ȃ���A�S�[����D���Ă��܂��܂��B
�@ �U���I�ɂȂ邱�Ƃ́A�U���ɐl���������ē������Ƃł���A���̂悤�ȍU���ɑΉ����邽�߂ɂ͐��I�ɑ���Ȃ��Ȃ�Ȃ��悤�ɁA����������悤�ɂȂ�܂��B
�@ ����͌l�Z�p�ł������ł��B�U���X�L����g�ɂ��邱�ƂŁA�������������K�v�����܂�A����������Ȃ�ƁA�����j�낤�Ƃ��čU�������������B
�@ �`�[���̃g���[�j���O�v��̒��ł��A������J��Ԃ��Ă������ƂŁA�U��̋������ł���Ǝv���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�i�T�j���̃v���[�͉��̂���
�@�h���u�������ӂȎq�̑I�����̓h���u���D��ł��B
�@�����O�L�b�N�����ӂȎq�́A�{�[��������X�y�[�X�ɏo���Ē����p�X���o�����Ƃ���ł��傤�B
�@���ӂȃX�L���������Ƃ͑�ł��B
�@�ł��A�T�N���ɂȂ낤�Ƃ��������ł́A�h���u���̂��߂̃h���u���A�p�X�̂��߂̃p�X�ł͂Ȃ��A�V���[�g�ɂȂ���v���[���ӎ����ăv���[��I�����Ăق����ƍl���܂��B
�@�I���`�[���ł��`�[���ł��u�Z�̔�I��v�ł͂Ȃ��̂ŁA�Q�[���ɏ����߂ɂ̓V���[�g��ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�V���[�g��ł��߂ɂ́A���A�����͂ǂ̂悤�ȃv���[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��f���邱�Ƃ��A�U���ł̗D�揇�ʂf����Ƃ������ł��B
�@�{�[����O�ɉ^�Ȃ���V���[�g���o���Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B�c�Ƀ{�[������荞�߂A����Ƀ{�[����n�����ƂɂȂ邩�A���˕Ԃ���Ă��܂��A�U���ɂȂ���Ȃ����Ƃ͑I�肽�����킩���Ă��܂��B���p�X�������Ȃ�����A�Ă���X�y�[�X�ɓW�J���邾���̃|�[�b�V�������J��Ԃ��Ă��Ă��A����S�[���ɋ߂Â����Ƃ͂ł��܂���B
�@�S�[���̐��ʋ߂��̊m���̍����ꏊ�ŃV���[�g��ł��߂ɂ̓{�[�����ǂ��։^�сA�l���ǂ��֑���Ȃ���Ȃ�Ȃ����B
�@�����邱�Ƃ��K�v�ł����A�S�[����D���Ƃ����������킩���Ă���̂ł�����A�|���Z�ł������Z�ł��悢�̂ŁA���@���l���Ăق����Ǝv���܂��B
�@�l����͂��v���[�̑I�������L���Ă����܂��B
|
|
|
|
|
�����P�U�@�f���\�[���̃C���^�r���[���̂Q |
|
�@�Q�O�O�X�D�Q�D�Q�W�@
�f���\�[���̃C���^�r���[���̂Q
�@�O��́A�h���u���̂��߂̃h���u���ł����Ă͂����Ȃ��B�Ƃ����b�����܂����B�������A�h���u���[�ɂ̓h���u�������悤�Ƃ��b�܂����B
�@����́A�h���u���̎����Ⴄ����ł��B�˔j���ӎ������h���u���́A����G���h�ŁA�S�[���ւȂ��铮�����C���[�W���Ă��܂��B�h���u���̂��߂̃h���u���͐�p�I�Ȉӎ����Ȃ��A�Ƃ肠�����|�[�b�V������Ԃł��B
�@
�@�t���[�̖��������A�X�y�[�X�����Ƃ����Ӑ}�������������ΐ�p�I�ȃC���[�W�������ł����A�R��A�S��Ɛ�Ԃ��h���u���͎���ɂ͂��蓾�܂���B�y�i���e�B�G���A�̃T�C�h�Ő�Ԃ��Ă��邤���ɁA�����ƌ����ԂɈ͂܂�Ă��܂��̂�����̃T�b�J�[�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@����́u�g�ݗ��āv�Ƃ������ɂ��ď����܂��ˁB
�@���{��\�̃Q�[�������Ă��Ă��A�f�t�F���X���C���ʼn��p�X���A�^�C�~���O�����ă{�����`�ɓ��Ă���A�T�C�h�ɏc�p�X�𑗂�����Ƃ����U���p�^�[��������܂��ˁB
�@�Q�[����g�ݗ��Ă悤�Ƃ��Ă���l�q�ł��B
�@ �q�������������悤�Ȏ��͂ł��܂��B
�@�f�t�F���X���C���Ń{�[�������Ƃ͂ł��܂��B���R���ł̃p�X�͔�r�I�e�Ղɉ��Ƃ��ł��܂��B
�@
�@�g�ݗ��Ă��ӎ��ł��Ă��邩�ǂ����A���̃p�X�̗l�q������Ɣ��f���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�T�b�J�[�̖{���́A����S�[���Ƀ{�[�������邱�Ƃł�����A�{�[�����c�ɉ^�Ȃ���Ȃ�܂���B���R�G���h�Ń{�[�������Ƃ́A����Ɏ���ɂ����̂ŁA�T�b�J�[�����Ă�悤�ł����A�{���ɂ����Ȃ́H�Ƃ�����������܂��B
�@
�@�c�Ƀ{�[��������Ƒ���{�[���Ɏ����A�˔j�̎�i�������A�h���u���Ő荞�ރX�L���������A�D��ꂽ���Ȃ��B������A���R�Ń{�[�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�܂�f���\�[���́u�ȒP�Ȏ���I������ȁv�Ƃ������������Ă��܂��B
�@���̂悤�ɁA�ȒP�Ȏ���I������Ǝ��̂悤�Ȍ��ۂ��N����܂��B
�u�O�����鎖�����Ȃ��悤�ɂȂ邱�Ƃł��B�v
�@������T�����Ƃ����ӎ��őO�����Ȃ��ƂR�{���S�{���f�t�F���X�Ń{�[�����悤�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������ł��B
�@ ����ɁA�f���\�[���͎��̂悤�Ȏ��������Ă��܂��B
������Ɠ���\���ł����A�ꏏ�ɍl���Ă݂܂��傤�B
�@�u���Ղ��e�v�ɑ���������������Ƃ������ł��B �v
�@�ǂ��������ł��傤���B���Ƃ��S�o�b�N���Ƃ��܂��ˁB���̑O�ɂ͂U�l�̃t�B�[���h�v���[���[������킯�ł��B
�@���肩��{�[����D���čU���ɐ�ւ����u�ԂɁA���̂U�l�����Ɉ��ɕ���ł��܂��Ƃ������ł��B
�@�悭�A�����ƕ��Ƃ��A���݂ƕ�������čU�����悤�Ƃ����܂����A�f���\�[���͂��̒��Ղ���邱�Ƃƌ����Ă��܂��B
�@���݁A�܂�A�I�肪�^���ɕ���ł��܂��ƁA���C���̑O��ɖ��ʂȃX�y�[�X���ł��Ă��܂��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�f���\�[���̍u�K��ɏo�����̎����v���o���܂������A�I�肪�^���ɕ��ԏ�Ԃ��s���w�E���܂��B
�@
�@�u���肦�Ȃ��I�v�ƒʖ�̕����w�E���܂��B
�@ ���Ղ��g���ăo�����X�悭�g�ݗ��ĂĂ������߂ɂ́A�O��̊W�̃|�W�V���j���O���K�v�Ƃ������ł��B�X�y�[�X�����肷����Ƃ������Ƃ́A�|�W�V���j���O�̃o�����X�������Ƃ������ɂȂ�܂��B
�@����ɂS�ڂ̎w�E�Ƃ��āA
�@�u�f�t�F���X���{�[����������A�c�Ƀp�X����ꂽ���ɁA���̌�̃v���[�������Ȃ��Ƃ������ł��B�v
�@�܂�A�p�X���ďI���A���Ƃ̓J�E���^�[�ɔ�����Ƃ����C���[�W�ł��B
�@�p�X������A�X�s�[�h�A�b�v���ă{�[���Ɋւ���Ă����Ƃ��A�������������悤�ȃX�y�[�X�ւ̑��荞�݂Ƃ��A�f�t�F���X�ł����Ă��N���G�C�e�B�u�ȓ������K�v�ł���Ƃ������ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@ �C���^�r���A�[�̕z���͎��̂悤�ɕ��͂��Ă��܂��B
�@�t�H���[�h������āA�^���Ƃl�e�̓g�b�v�ɕ��Ԃ悤�ɓ����Ă��܂����Ƃ�����B�܂��A�{�����`���f�t�F���X���C���ɋz�����܂�Ă��܂��B
�@�������l�Ɋ����Ă��܂��B�W���j�A�A�W���j�A���[�X�̃T�b�J�[�����Ă���ƁA���Տȗ��̍U�炪�����܂��B
�@�܂�A�{�[�����������I�肩��̃p�X���~�����C�������牡�ɂ��Ă��܂��A���ʂƂ��ĕ���ł��܂��ƌ������ł��B
�@�f�t�F���X�����l�ŁA����I�͂l�e�̑I�肪����{�[���ɂȂ����u�ԂɃZ���^�[�o�b�N�ƕ���ł��܂��܂�A�����Ă��܂��Ƃ������������܂��B
�@�l�e�Ƃ͂e�v�̈���ł��Ȃ����A�c�e�̈���ł��Ȃ��A�l�e�Ȃ̂��ƍl���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�ł́A�ǂ̂悤�Ȏ����ӎ����ăT�b�J�[������悢�̂ł��傤���B
�@�R�U�O�x���痈��v���b�V���[�̒��ŁA�N�_�ƂȂ�v���[�����邽�߂ɂ̓e�N�j�b�N�A�l��p�A�̗������K�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�f���\�[���͓��{�l�̓{�[�����������܂����A�t�b�g�{�[�������Ă��Ȃ��Ƃ����w�E�����Ă��܂��B
�@�u��̓I�ɂ́A�|�W�V�������̕��ƂɂȂ��Ă���Ƃ������ł��B�v
�@�O��̕��Ƃƌ������ł��ˁB
�@�e�v�C�l�e,�c�e�̕��Ƃ�������Ƃ������ł��B
�@ �f�t�F���X���U���Ɋւ���Ă����A�e�v���O���Ŏ��������A�S���ōU�炩������Ă��������t�b�g�{�[�����Ƃ����������������悤�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�{�����`�Ƃ����|�W�V�����ɂ��āA�f���\�[���̃R�����g�͎��̒ʂ�ł��B
�@�u���{�̃{�����`�̓{�[����D���Ă��Ȃ��B�t�����X�ł̓{�����`���{�[����D���l�ƌĂ�ł���v ���̃R�����g���āA�n�b�Ǝv�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�Ⴆ�Β��c�p�I�肪�{�����`�����Ă������{�ł́A�����������{�����`�̃C���[�W�ł����B
�@���݂̏��w���⒆�w���ɂǂ��̃|�W�V������肽���H�ƕ����ƁA���Ɏ��M�̂���q�͂قƂ�ǂ��{�����`���g�b�v���ƌ����܂��ˁB
�@���{�ł́A�{�����`�Ƃ����ƍU���I�ȃC���[�W������܂����A���E�ł́u�{�[����D���l�v�Ȃ̂ł��ˁB
�@�e�b�����̍���I��Ȃǂ́A�{�����`�ɋN�p�����Ɓu�{�[����D���l�v�ɂȂ��Ă��܂��B�{�l�́A�s�����̂悤�ȃv���[���������ƌ����Ă�����������܂������A�{�[����D���A�J�o�[�ɓ���\�͂͑f���炵�����̂�����܂��B�a���ڗ����Ă��܂��ˁB
�@���̃R�����́u�琬�v�܂�A��\�`�[���̕��͂��s�����̂ł͂Ȃ��̂ŁA���A�W���j�A��W���j�A���[�X�ł́A�ǂ̂悤�Ȏ����ӎ����ăg���[�j���O��Q�[�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�ɂ��ď����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�f���\�[���͎q�������̔N��ɂ́A�ǂ�ǂ��ʒu����{�[����D���ɍs������ׂ����A�ƌ����Ă��܂��B
�@�ł��A���w�R�N���܂ł̎q���B�͎�������܂�D���łȂ��A�U�����D�ތX��������܂��B�S�[�������ӎ��������Ƃ͌����܂���B
�@�@
�@���Z���܂�P�U�ɂȂ��Ă�������g�D�I�ɍs�����߂̎w�����K�v�ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B
�@�琬�N��ɕK�v�Ȓ͎��̒ʂ�ł��B
�@ �u�q�ǂ������Ƀt�b�g�{�[����������v �S���U���A�S�����������ǂ��A�����͎�������Ȃ�������Ȃ��B
�@�A�J�f�~�[�̑I�肽���́A�i�̉����`�[���ƍU�ߍ�����5-6�ŕ�����������U��Ԃ�A�����悢�v���[���Ƃ�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă��܂��B
�@
�@�u�܂��{�[����D�������A�U���ł��鎞�͍U������B�U������������B�����s���鎞�͑�������B���ꂪ�t�b�g�{�[�����B�v
�@�@�f���\�[���̌��t�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�D�揇�ʂ́A�y�����t�b�g�{�[�������鎖�B
�@�悢�v���[�Ƃ͉�����m�邱�ƁB�悢�v���[�Ƃ́u���������v���[�v�Ǝv�����B
�ȒP�Ƀ^�b�`���C��������Ȃ��A�Ӑ}�̂Ȃ������O�L�b�N�����Ȃ��A�Ȃǂ��������Ă��܂��B
�@�P�T�܂ł͍U���A�P�U����n�[�h�ɓ�����ɍs������Ƃ������ł悢�̂ł͂Ȃ����A�ƌ����Ă��܂��B
�@���́A�����ōl���܂����B���Ȃ��Ƃ��������Ō��Ă���琬�i�K�̃T�b�J�[�́A���ʂ����߂邠�܂�A���Ƃ͌����邵�A�|�W�V�����̌Œ艻�������܂��B
�@
�@�A�J�f�~�[�ł̍l�����������w���ҒB�͂ǂ̂悤�ɉ��߂��āA����ɔ��f������ׂ��Ȃ̂��B
�@�q�������������Ȃ��Ƃ��P�W�ł�����x�������ꂽ�t�b�g�{�[���[�ɂȂ邽�߂ɂ́A�e�N��Őg�ɂ���ׂ��ۑ肪����ƂƂ��ɁA�t�b�g�{�[���̖{������������������ӎ����Ă������Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��ƍl���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�A�J�f�~�[�ł́u���v�͂̌���v�ɂ��ϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B����T�b�J�[�A���N�T�b�J�[�������ł����A�A�������U��A�n�[�h���[�N�̂��߂ɂ́u���v�́v���K�v�ł��B
�@���v�͂�����Ƃ����ƁA�f������C���[�W���܂����A�{�[�����g���Ď��v�͂��グ��H�v�����Ă��܂��B
�@�f����̕����������悢���Ƃ��f���\�[���͔F�߂��A�{�[�����g���Ď��v�͂��グ�邱�Ƃɂ�������Ă��܂��B
�@�C���^�r���[�ɂ͂���܂��A�����ŁA�w���҂ɑ��Ă��u�ȒP�ȑI�������Ȃ����v���������Ă���悤�Ȋ��o���܂����B
�@
�@�{�[�����g���ĐS�����𗎂Ƃ��Ȃ����j���[��I�[�K�i�C�Y���l���邱�Ƃ́A����ł��B
�@�g���[�j���O�̉^�c��������̂�����܂��B�O���E���h�����邮�鑖�点�ă^�C����}�鎖�͊ȒP�ł��B���ʂ�����ł��傤�B
�@�ǂ��ł��傤���A�琬�Ɋւ�闧��̃R�����g���āA�䂪�q��䂪�`�[���̑I�肽���̎����l����Ɖ������ׂ����B
�@�f���\�[���̌����ʂ�ɂ��ׂ��Ƃ������ł͂���܂���B
�@�f���\�[���̌��t���āA�ǂ������T�b�J�[�����Ă������A�w�����Ă������A�����͉���`����ׂ����A�Ƃ������ł��B
�@�f���\�[���͎q���������琬���ăv���ɑ���d���̃v���ł��B
�@���̂悤�Ȏw���҂��C�O�ɂ͂������܂��B
�@�v����ڎw���A�T�b�J�[����B�������Ƃ������͂ǂ�Ȃ��ƂȂ̂��B
�ꏏ�ɍl���Ă����܂��傤�B
����̃e�N�j�J���j���[�X30���ɂ��A�ڂ��\�肳��Ă��܂��B
|
|
|
|
|
no15 JFA�e�N�j�J���j���[�X29�����f���\�[���̃C���^�r���[ |
|
�@�Q�O�O�W�D�Q�D�U
�@�`�T�v�`
�@�N���[�h�E�f���\�[���ɁA�z�[��Y�Z�p�ψ���ψ������C���^�r���[�����L���Ƃ��f�ڂ���Ă��܂��B�R�N�Ԃɂ킽��JFA�A�J�f�~�[���w�������f���\�[���͓��{�T�b�J�[�ƈ琬�ɂ��Ăǂ̂悤�Ɍ��Ă����̂��܂Ƃ߂Ă��܂��B�e�N�j�J���j���[�X���w�ǂ���Ă��Ȃ����ɁA�v�Ă��`�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�����{�ɂ͗ǂ��I�肪���� �f���\�[���͂��������Ă��܂��B
�@�������A�ǂ��I�肪���Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B����́A�ǂ��w���҂��܂��܂����Ȃ�����Ƃ������Ă��܂��B�f���\�[�����G���[�g�v���O�����Ƃ��Ĉ琬�������N�B���A���݂�U16���{��\��5�C6�l���邱�Ƃ��画�f���Ă��A�ǂ��I���ǂ��w���҂��w�����邱�Ƃɂ��ǂ��I�肪����Ă����Ƃ����m�M�̎����Ă���悤�ł��B
�@�C���^�r���A�[�̕z�����u�ǂ��I��Ƃ͂ǂ������I�肩�v�Ƌ�̓I�ɕ����ƃf���\�[���͂��������܂����B
�@�u�_�C�i�~�b�N���v�u�r�q���v�u�_��v�u�������ԑ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ɓv�u�N�I���e�B�v �����ǂ�Ŏ���������l���Ă��邱�ƂɋC�����܂����B
�@
�@����́u�_�C�i�~�b�N���v�Ƃ����_�ł��B�g���Z�����w�����Ă���ƁA�_�C�i�~�b�N�ȑI��͖ڗ����܂��B�_�C�i�~�b�N�ȃv���[������q�́A�e�N�j�b�N���z�����A�����ʂ������A���ʂƂ��ăT�b�J�[�I��Ƃ��ĐL�т܂��B
�@�_�C�i�~�b�N�Ƀv���[���邱�Ƃ����{�l�̃|�W�e�B�u�Ȗʂł���ƃf���\�[�����Ƃ炦�Ă��邱�Ƃ���A�_�C�i�~�b�N�ȃv���[�������o�����Ƃ���X�R�[�`�̖����̂ЂƂł͂Ȃ����A�Ƃ��l���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@���t�����X�̎q�������͂����Ƒ����Ă��� ���{�ƃt�����X�̎q�������̃g���[�j���O�ƃv���[���r����ƁA���{�l�͂܂��܂�����K�v������ƃf���\�[���͌����Ă��܂��B
�@���{�l�����Z���̃T�b�J�[�ł͑���ʂ��A�b�v���āA���E���x���ɒǂ������������ł����A���w�ȉ��̃��x���ő��邱�Ƃ��������Ă���A���Z���x���ł͐��E��ǂ����������s�\�ł͂Ȃ��Ƃ������ł��B
�@���w�����w�N����A�����Ƒ����悤�Ƀg���[�j���O���Ă������ƂŁA���l�����Ƃ��̃��x��������ɍ����Ȃ�Ƃ����u��グ���ʁv�����҂ł��邵�A���{�l�͂�������ׂ��Ƃ������Ƃł��B
�@�I�V�������A���{�l�͂܂��܂�����ʂ�����Ȃ��ƌ����Ă��邱�Ƃɂ��Ă��A�m�肵�Ă���A����ɑ��邱�ƂƐ��m�ȃv���[�����߂Ă����ׂ��ƌ����Ă��܂��B
�@�{�[�����g�����g���[�j���O�Ńe�N�j�b�N�Ǝ��v�͂��ɍ��߂Ă������Ƃ���Ƃ������ł��B ���͂����ǂ�ŁA�`�[���ł̃g���[�j���O��U��Ԃ�܂����B�`�[���ł̃g���[�j���O�ł̓{�[�������̃����j���O��荞�݂����܂���B
�@���v�͂����邽�߂ɑ��肱�ނ��Ƃ́A�l���x���ł��邱�Ƃł���A�`�[���ł̗��K�ł̓{�[�����g�����g���[�j���O�ŁA���v�͂ƃe�N�j�b�N�����コ���郁�j���[��������邱�Ƃ������I�ƍl���Ă��܂��B
�@�f���\�[�����w�����Ă�������JFA�A�J�f�~�[�ł́A�S�����𗎂Ƃ��Ȃ��H�v�������ɂ���܂��B���w�����x���ł��ꕪ�Ԃ̐S�������P�U�O��ŃL�[�v����悤�ȃg���[�j���O���Q���ԋ߂������邱�Ƃ́A���v�͌��ゾ���łȂ��A�����S�����̒��ł����m�ȃe�N�j�b�N�����邱�Ƃ�v�����Ă���ƌ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@���L���ȃe�N�j�b�N�Ƃ͉������{�ƃt�����X�̍������v�͂ƗL���ȃe�N�j�b�N�̍��Ƃ������Ƃ��킩��������ǁA�L���ȃe�N�j�b�N�Ƃ͂Ȃɂ��B
�@�f���\�[���͂��������Ă���B�u�h���u���̂��߂̃h���u���ɂȂ�Ȃ��v�u�p�X�̂��߂̃p�X�ɂȂ�Ȃ��v �h���u���͓˔j���邽�߁A�V���[�g���邽�߂̂��́A�p�X�����邽�߂̂��̂ł���B
�@���{�̎q�������́A�h���u�������邱�Ƃɖ������ă{�[���������Ă���̂ł͂Ȃ����B���������q�́A�{�[���������h���u��������q�̓��x���̍����T�b�J�[�ɐi�ނƂ���Ƀ{�[��������������B�f�t�F���X���g�D�����Ă���ƃh���u�������ł͒ʗp���Ȃ��B
�@���͂��̃R�����g��ǂ�ŁA�h���u�����ǂ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�h���u�������I�������Ȃ����Ƃ��ǂ��Ȃ����Ƃł���A�h���u���̂��߂̃h���u���ɂȂ�Ȃ����ƌ����Ă���Ɨ������Ă��܂��B
�@����Ƀf���\�[���͂����������Ă��܂��B �h���u���[�̓h���u�������ׂ������A���{�l�ɂ̓h���u���������Ă���B
�@���K���@�ɖ�肪����B�h���u���̂��܂����肾���̗��K�ł͂Ȃ��A�h���u���̂��Ƃ̃v���[�ɂȂ�����K�����Ȃ���ΈӖ����Ȃ��Ƃ������̂ł���B
�@�˔j�̃h���u���ł���V���[�g�ŏI��邱�ƁB
�@�������̕����ɂ͋������܂��B�h���u���̂��߂̃h���u�����K���ƁA�S�[���O�ʼn��x����Ԃ��ăV���[�g����Ȃǎ���ł͂��肦�Ȃ����Ƃ̗��K�ɂȂ��Ă��܂��A�܂��������A���e�B�Ɍ�����B
�@�����������ɁA�h���u���[�Ƃ��Ă̑f������������A�h���u���������܂��B���s�����R����܂��B����������������܂��B�������A�h���u����˔j�̓���Ɏg������v�����܂��B
�@���ՂŃ{�[�������������Ă݂���A�X�s�[�h�A�b�v�����ʂŃh���u�������ăX���[�_�E������悤�ȃh���u���̓}�C�i�X�ł��B
�@�@����ɁA�C���^�r���[�͑����܂����A�܂����T�̃R�����ŁB
|
|
|
|
|
�����P�S�@���{�T�b�J�[����͂���ȕ������l���Ă���i�u�K���̃��|�[�g�j |
|
�Q�O�O�X�D�P�D�Q�W
�@�@�`�Q�O�P�T�N�͂��������������I�@�`
�@�Q�O�O�T�N�錾�͂����m�ł��傤���B
http://www.jfa.or.jp/archive/jfa/2005/
�@�Q�O�P�T�N�ɂ͐��E�̃x�X�g�P�O�ɓ���v���W�F�N�g�ł��B����̓g�b�v�`�[�������łȂ��A���N���A���[�X���A�w���҂��A�g�D�����ׂĂł��B�t�Ƀg�b�v�`�[���������x�X�g�P�O�ɓ������Ƃ��Ă��オ�Â��Ȃ��ł��傤�B���L�V�R�̓����_���̂悤�ɁB ���[���h�J�b�v�ɂ͂ő����邱�Ƃ��K�{�ł��B
�@���̂��߂ɂ́A���N������g�b�v�`�[���Ɠ����l�����̃T�b�J�[������K�v�����邱�Ƃ��A�h�C�c�A�X�y�C���A�t�����X�������Ă��܂��B �h�C�c���[�J�b�v���T�����h�C�c�A���[���Q�O�O�W�ŗD�������X�y�C���A�t�����X���[���h�J�b�v�ŗD�������t�����X�Ȃǂ́A���̂悤�ȑg�D���̍s���͂ɂ�茋�ʂ��o�������͎����ł��B���̂悤�ȋ����V�X�e�����A�h�C�c�ł͂S�O�O��A�t�����X�ł͂U�O�O������Ƃ����̂ł��B �������܂��ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�i�P�j���E�̃T�b�J�[�ɋ߂Â��w�͂�����B����́A�A�W�A�ɂ����闧���ʒu������āA�����d�����ƂƂ��ɔ����͂����߂Ă����Ȃ��ƁA�I�[�X�g�����A��J�^�[����UAE�Ȃǂ̂悤�Ƀ^�����g�Ǝ����͂̂��鍑�ɑ��ĕs���ɂȂ�Ƃ������̂ł��B
�@
�@�P�����h�C�c�Ŗ{���o�ł��Ă��܂��B���̃T�C�g�́A���[���b�p�ɋ߂��T�C�g�ƌ����܂��B���A���{�T�b�J�[�����Ǝw���҂̋����ɕK�v�Ȃ̂����ł��B
�@
�@�A�W�A�̏��A���[���b�p�̏��ł��B�t�����X�A�h�C�c�A�X�y�C�����r�b�O�^�C�g��������Ă���͍̂����グ�ď��N�`���[�X����̋����琬�Ɏ��g�ލs���͂̐��ʂł��B
�@�i�Q�j�g�b�v�`�[�������̋����ł͑�������������B���L�V�R�̓����_���ȍ~�̒���ƁA�O��̃��[���h�J�b�v�ł̐킢����U��Ԃ�ƁA�g�b�v�`�[�����������ł́A�A�����ă��[���h�J�b�v�ɏo�ꂷ�邱�Ƃ͓���A���[�X�N��A�W���j�A���[�X�A�W���j�A�N��̋����琬����ł��邱�ƁB �����A�L�b�Y�v���W�F�N�g�Ƃ��ď��w�������̎q�������̃v���W�F�N�g���i�s���Ă���A���ʂ��łĂ��܂��B
�@�i�R�j�^�C�g������邱�Ƃƈ琬���邱�Ƃ̃o�����X���w���͑S���{���N�T�b�J�[���ł̃^�C�g����ڎw���đ��g�܂�Ă��܂��ˁB
�@���݂͉Ăɖ{���s���Ă��܂��B�H�ȍ~�́A�G�A�|�P�b�g��ԂƂȂ��Ă��܂��܂��B ���w���̈�N�Ԃ͔��甭�B�ƋZ�p��p�̏�B�������A�t�Ɠ~�ł͕ʐl�A�ʃ`�[���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���w���Ɉڍs���₷�����邽�߂ɂ��A���̑����P�Q���ɊJ�Â���Ƃ���������������Ă��܂��B �P�Q���܂ł́A�S���{���ւ̎Q�����邽�߁u���[�O��v�����邱�Ƃɂ��Q�[�����s���ă`�[���͂̋����ƃ^�C�g����ւ̎Q�����鎖��ڎw���Ƃ���������������Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@ �i�S�j11�l������̒E�p11�l���A�R�l�R���ɂ��A��l�T�b�J�[�����������������̃T�b�J�[�ł́A���炽�Ȃ��A�X�L���̏�B�ɂȂ��镔�������Ȃ��Ƃ����f�[�^�����邱�Ƃ��獡��͂W�l���A�P�l�R���ɂ��R�N�H�[�^�[���̓����ɂ��A�ȉ��̖ړI�B����}��B
�@ �@�S�����Q�[���Ɋւ����Â���
�@�A�{�b�N�X�i�y�i���e�B�G���A�j����{�b�N�X�ւ̃X�s�[�f�B�[�ȍU�h
�@�B�Z�p���x���̔��f�ƏK���̖��ĉ�
�@�C�X�y�[�X�Ǝ��Ԃ�D�������T�b�J�[�ւ̏K�n�Ȃǂł���B
�@
�@ �R�N���ȉ��͂T�l���Ȃǂɂ��A�U��ɑS�����ւ��Q�[���ɂ��X�L���A�b�v��}���Ă������Ƃ���������Ă���B ���̂��߂̑��łȂ��A���{��\�̋����ɂ́u�v�̈琬���ŏd�v�ۑ�ł���A�̈琬�̂��߂ɂ̓Q�[���̂�������ǂ�ǂ�ς��Ă����B �{�[���ɐG���A��������ʂ𑽂����A�U��̐�ւ��Ɖ^���ʂ��グ�Ă����B���̂悤�Ȋ����v�ւ̋�̓I��g�ƂƂ��Ɏw���҂ɋ��߂��邱�Ƃ̓T�b�J�[��i���ł��郈�[���b�p�����̏���ϋɓI�Ɏ��W���A���{�̃T�b�J�[�ɔ��f�����Ă������ƁB���E�I�ɂ͒n���I�s���ł͂��邪�A�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��n�[�h���ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�i�T�j�P�U�łقڊ��������鍑�̂͌��ǂ����̐킢�ł��邪�A����͎w���͂�w���g�D�̐킢�ł�����A�P�U�Ő��ʂ��o�����߂ɂ́A�P�T�A�P�R�A�P�S�A�P�Q�A�P�P�ƃJ�e�S���[���Ƃ̐ςݏグ���K�v�ł���A�������S��̃R�[�`�͂P�U�̍��̑�\�I��̓y��ɐG��Ă��邱�Ƃ��ӎ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�P�Q�̏��N�̂S�N��͂����Ƃ����Ԃɗ���B ���̂悤��JFA�̃��[�h�}�b�v�ɑ��A����ł͂ǂ̂悤�Ȋ������s���Ă����悢���B ���ׂẮA�����X�y�[�X�A�����X�s�[�h�ł̃X�L���A�b�v�̂��߁B
�@�{�[���ɐG���A������铮���𑽂����Ă����B
�@ ���̂悤�ȃA�N�V�����v���O�������J�n����Ă��钆�ŁA�q�������̂��߂ɉ������Ă���̂��B �T�b�J�[�����ɂȂ�����B���ɂȂ��āA�����ŏ������ړI�̂͂��ł��B�����ŏ����߂Ƀg���[�j���O���K�v�ł��B�����Ď����ŏ��̂́A�l�l�̗͂̌��W�̌��ʂł���ׂ��ł��B
�@�w���ҁA�ی�҂��܂߂���l�������ւ��Ă����K�v������ł��傤�B
�@�u���O����}�K�ŏ��M���Ă����܂��B�F����̏������҂����Ă��܂��B
�@
|
|
|
|
|
�����P�R�@���Z�T�b�J�[�̑f���炵���킢���������z |
|
�Q�O�O�W�D�P�D�P�V
�@��87��S�����Z�T�b�J�[�I�茠�A���N��������^���Ă���܂����B
�@�����̍L���F���Ǝ������鐼�̐킢�́A���Ɍ��������̂�����̂ł����B��T�Ԃ��������ł��A�^����J��Ԃ����Ă��܂��B
�@�鐼�̑唗�E�Ɩ쑺�͒��w����U�N�ԃc�[�g�b�v��g�ݑ����āA�����ł́A�P�O���_�ƋL�^��h��ւ��܂����B �唗�E�̃X�L���͊m���ɍ����ł����A�{�[�������Ȃ���Γ��_�ł��܂���B�쑺�Ƃ̑��̍������v���[�̐��ʂ��P�O���_�Ƃ����L�^�̂ł��傤�B
�@��������т��ăT�b�J�[����Ƃ������͎��͗��z�I�Ȋ��ł��B �g���Z���͂P�U�܂łł��B�P�U�Ƃ������Z���ł����A���w�ƍ��Z�̂U�N�Ԃ���̃N���u�Ŏw����������͂��������͂���܂���B���̔N��́A�v�����[�X����Ƃ��āA��Ϗd�v�ł��B
�@�s��͂��܂�������F���Z�̑I�肽�����A�Z�]��FC�ȂǃW���j�A���[�X�N���u�o�g�ł��B�܂�A������т����T�b�J�[�����Ă���Ƃ������ł��B �����Ȓ��̌������Z�����N�S�����Ɋ���o�����͕����̎��ł͂���܂���ˁB�I��́A���C�h�C������ł�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@���āA�D�������F���ł����A�w���҂Ƃ��Ă͓���ē̎w������ϋ���������܂����B 35�B�ēQ�N�ځA�w�����V�N�ځB���C�h�C���L���B�I�肽���̃v���[������ƁA��{���������肵�Ă��鎖�ɋ�������܂��B
�@���Ƃ��A�������{���[�V���[�g�̃V�[��������܂����B����Ńt�F���X�ɑj�܂�܂������A�R�[�X�A�^�C�~���O�Ƃ��҂����荇���Ă��܂��B ���̑��ׂ����v���[�ЂƂ��ЂƂ��u�e���v���Ȃ��A���ߍׂ����Z�p�w���̂������ƌ�����ł��傤�B
�@�܂��A��p�ɂ��ẮA�鐼�ΑO����p�̃Q�[�����͂���������I�肽���ɐZ�����Ă���Ȃ��Ǝv���܂����B �唗�E�ɉߏ�ȃ}�[�N������킯�ł��Ȃ��A���Ƃ����ăt���[�ɂ͂����Ȃ��B
�@���狭�U�����b�g�[�Ƃ��邾�������āA�U���̂��߂̃f�t�F���X�̈ӎ������������ł��ˁB ���ՂŃ{�[����D������̃X�s�[�h�A�b�v�́A�鐼���߂鎞�Ԃ�^���܂���ł����B�ЂƂ�ЂƂ�̈ӎ��̍����Ɛ�p�����̌��ʂł��傤�B
�@���j�[�N�Ȃ̂͂X�ԋ����I��ł��B�Q���_�̊���ł������A�Z���^�[�������ĕٌ�m�ɂȂ肽���Ƃ̎��B���Ў��������Ăق������̂ł��B �T�b�J�[�I��Ƃ��Ă̂ЂƂ̑I���ł��ˁB
�g���Z���őI�ꂽ�I��́u�v���v�ɂȂ肽���ƌ������낦�Č����܂��B�ł��A�v���ɂȂ��̂͂ق�̈ꈬ��ł��B �����ȍ��Z������o�āA�Љ�l�ɂȂ��Ă��T�b�J�[�𑱂��Ă���v���[���[�͑��ɂ����܂��B �Љ�l���[�O�ł��B�ނ�͍��Z����ɃT�b�J�[�����A��w���o�����A���Ƃ��Ċ�ƂɏA�E���āA�T�b�J�[�𑱂��Ă��܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@
�@����A�v�������ނ������g�I��͔֓c�ł̎w������]���Ă���悤�ł����A���{��\�Ƃ��Ď����z�������g�I��̎w���҂Ƃ��Ă̎�r�Ɋ��҂��Ă��܂��B �ł́A���̑������̌��������ނ��������̂i���[�K�[�͂ǂ�Ȑi�H�����ǂ��Ă���̂ł��傤���B �@
�@�v���ɂȂ����ŖړI���ʂ������Ƃ������ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�T�b�J�[�����o����A�����ł��Ȃ��Ă������Ƃ������R�ɂ͂Ȃ�܂���B ���c�i�p�j���A�B��ł͗D�����ł����B���݂��m�I�Ȋ����𑱂��Ă��܂��B
�@�T�b�J�[�̗��K�Ɏ��Ԃ��������Ƃ������킯�ł͂Ȃ��̂ł��B�T�b�J�[�����m��Ȃ������u���v�Ƃ������ł��B
�@���w�Z���獂�Z�̑����Ȑ���ɂ́A���{�Ƃ���Ƃ����h������������Ăق����ƍl���Ă��܂��B �g���Z���̏�́A�I���̏�ł�����܂����A�l�i�`���̏�ł�����܂��B �悢�Ӗ��Łu��l�ɂȂ�v���ŁA�T�b�J�[���t���[���������̂ɂȂ�ł��傤�B
�@ �ȏオ�A���Z�T�b�J�[�̑f���炵���킢���������z�ł��B ������߂�ȁA�����悤�A�������āB
�@���ׂāA��������I
�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
|
|
|
|
|
�����P�Q�@�m�`�a�n����I�T�b�J�[�����\�z�} |
|
�@�@�@�Q�O�O�X�D�P�D�T
�@�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
���N�����̃R��������낵�����肢���܂��ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@���N�͌��U����A�K���o���̑f���炵���T�b�J�[�ɐ�������܂����B
���{�̃T�b�J�[�́A���̃K���o�T�b�J�[��ڎw���ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ��������������܂����B�K���o�̓f�t�F���X���C���ɏ��X�E�B�[�N�|�C���g������܂����A���Ղ���g�b�v�ɂ����ẮA�U�ߋ}�����A�|�[�b�V�������璆���˔j�̏c�p�X��_���Ƃ����������x���J��Ԃ��܂����B
�@���̃|�[�b�V�����T�b�J�[�́A�P�O�O���p�X����������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�{�[����D����f�t�F���X�ɉ���ă{�[�������߂��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B �K���o�͂��́u�{�[����D���v����G���h�ōs���Ă��܂����B����ɁA�J�E���^�[�̃s���`�ɂ̓n�[�t�̉�������������߂��ă��X�g�p�X���J�b�g�����ʂ�����܂����B
�@�|�[�b�V�����̋Z�p�����łȂ��A�|�[�b�V�������x����^���ʂ͂������N���u���[���h�J�b�v�R�ʂ̃`�[�������̎��͂���܂��B �ȒP�Ƀp�X���Ȃ��ł���悤�Ɍ�����K���o�̃v���[�ł����A�����D���ɍs���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�D���ɍs���Ȃ��̂ł��B���ՂɒD���ɍs���āA�����c�[���琔�I�s��������Ă��܂��A�K���o�ɂƂ��Ắu�҂��Ă܂����v�Ƃ�����ʂɂȂ�܂��B �����^�b�`�A�c�[�^�b�`���܂����ă{�[�����K���o�̒��Ղ����Ă���ƁA�T�|�[�g����I�肪�悭�����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B���^�[������̂��A�����Ď�̂��A���ɃR�~���j�P�[�V�������Ƃ�Ă��܂��B
�@���{�Ɖ������|�W�V�����`�F���W��������ʂ�����܂������A����ē̎w���ł͂Ȃ��A�t�B�[���h�v���[���[�B�̔��f�ɂ����̂ƌ�Œm���āA�A�W�A�`�����s�I���̔��f�͂̃��x���������܂����B �x���`����̎w���łȂ��A�����B�Ń|�W�V������ς���^�C�~���O�����������Ȃ��A���s���Ă������͂���܂ł̓��{��\�ł��Ȃ��Ȃ��������ʂł͂���܂���ł����B
�@���[�_�[�V�b�v����鉓���̔��f������܂����A�`�[�����C�g�����̔��f������āA���̈Ӑ}�ɉ����ē������Ƃ��ł���Ƃ������͑f���炵�����Ƃł��B ���{�̃T�b�J�[���A���x�����ЂƂオ�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������o�����o���܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�K���o�ɂ���������ꂽ�_���������̂́A�f�t�F���X�ł��B �u�����Ń{�[����D�����I�v�ƌ��߂���A��l�ł͂Ȃ��A��l�A�O�l�Ń{�[����D���ɍs���āA�U���ɂȂ���B���̃����n���ɂ́A���ɂȂ����̂������܂����B �́A�N���C�t�̂����I�����_�`�[���́u�g�[�^���t�b�g�{�[���v�ł́A�U�����ɂ́A�|�W�V���j���O�����[�e�[�V�������Ȃ��瑊���f�킵�A����{�[���ɂȂ����u�ԂɁu�{�[�����v�Ə̂��āA�����Ń{�[����D���ɍs���Ƃ����V�[���������܂����B �N���u���[���h�J�b�v�ł̌o������A�{�[����D���u�^�C�~���O�v���`�[���S�̂ɐZ�����Ă������ƂƁA�D�����u�ԂɍQ�Ă邱�ƂȂ��A�|�[�b�V�������Ȃ���A�X�y�[�X�ɓW�J���Ă����l�q�́A�W���p���T�b�J�[�̎�{�ƌ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B
�@�����f�t�F���X�A�t�H�[���[�h������킯�ł��Ȃ��A���[�J�X���O���ň��肵���v���[�������Ă��܂����A�|�C���g�Q�b�^�[�ł͂Ȃ��`�����X���[�J�[�Ƃ��Ă̓����ɓO���Ă��܂��B �P�V�O�Z���`�ȉ��̑I�������K���o�ł����A���{��\�����E�ɂ�����u�����ʒu�v�Ǝ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@
�@���̂悤�ȃQ�[�������āA�琬�N��ɂ͉����K�v���l���Ă݂܂����B �܂��́A�ȒP�����Ɍ�����u�V���[�g�p�X�v�ɂ��|�[�b�V�����ł��B ����͏��w�����璆�w���ɂ��K�v�ȋZ�p�ł����A�����Ȃ���̃v���[�̘A���ł̐��m�ȃp�X���[�N�̊�{�͂�͂�A�L�b�N�ł��B�C���T�C�h��A�E�g�T�C�h�ł̃p�X�ł��B�����āA�悢�̐��Ńp�X���o���A�p�X����Ƃ����u��{�v���O�ꂳ��Ă���̂ŁA��Ƀp�X�R�[�X������܂��B
�@����ɁA�����ăp�X����A�p�X���o���Ƃ��������J��Ԃ��Ă���̂ŁA���̓C���^�[�Z�v�g��_�������Ȃ��Ȃ��ł��܂���B �c�ɓ����{�[�����m���̒Ⴂ��ʂł́A�����������A�{�[���������܂��B���p�X���������āA�c�ɓ����^�C�~���O��_���Ă���Ƃ���Ɂu�|�[�b�V�����̂��߂̃|�[�b�V�����v�ł͂Ȃ��A�u�U������^�C�~���O��}�邽�߂̃|�[�b�V�����v�Ƃ����������܂��B
�@�����_�ƂȂ����d�˂̃S�[�����A�����̃p�X����`�����X�����܂�܂����B�S�[����_�����ʂł͐ϋɓI�ɃS�[���Ɍ������B�����Ɣ��f���ăT�C�h�Ƀ{�[�����U�炷���ƂȂ��A�����ǂ����}�����v���[�������_�ƌ�����ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@���̂悤�ȃT�b�J�[�́A���w�A���w�A���Z�̈琬�N��ł͕s�\�ł��傤���B �������A�u�����ǂ���v�̊��o�Ɓu�����Ȃ画�f��ς���v���́A���w���̃T�b�J�[�ł��K�v�ƍl���܂��B ����{�[���ɂȂ�u�{�[�����v�����Ă��A�{�[����D���ɍs���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���̎��Ԃ͑���̎��Ԃł���A�V���[�g��ł����\��������܂��B ����{�[���ɂȂ����u�ԂɁu����ɃV���[�g��ł����v�u���̃V���[�g�Ŏ��_���邩���m��Ȃ��v�u�����ʒu�Ń{�[�������A�V���[�g�`�����X�ɂȂ���v�Ƃ����A�u�A���[�g�v�̈ӎ��������Ƃ́A���w���⒆�w���ł��K�v�Ȏ��ł��B
�@���āA���Z�T�b�J�[�ł́A���҂����`�[�����P�C�Q���Ŕs�ނ��A�����A�x�X�g�S�����܂�܂����B �܂��������̐����Ԃ̃T�b�J�[�͖ڂ������܂���B�����ɓ��肵�Ă���唗�I��͂����Ԃ�O���璍�ڂ���Ă��܂������A���̑��ł͂P�����Q���_���S�����A������Ƃ��������𑱂��Ă��܂��B �V���[�g�V�[������������ƁA�唗�I�肪���܂��Ƃ�����ۂ��܂����A���킩��̃V���[�g�ł͂Ȃ��A�J�E���^�[����̍U������̓��_�������悤�ł��B
�@����`�[�����}�[�N�����Ă���̂ł����A�u�ԓI�Ȑ�Ԃ���A���Ԃ����܂��g���v���[�́u�����Z���v�ł��B�s����Ԃ���AGK�̋t�����v���[���o����I��͑��ɂ����܂����A�m���Ɍ��߂�Ƃ�������͂́u�Z���X�v�������܂��B ���̑唗�I�肪�ǂ̂悤�Ɉ���Ă������A���ꂩ��ǂ̂悤�ɐ������Ă������B���͂�ǐՂ����Č������邱�Ƃɂ���āA���{�́u�X�g���C�J�[�s���v�̉����ɖ𗧂̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B
�@�K���o�ł͔d�˂������_�����߂܂������A�^�C�g���̂��������v���b�V���[�̂������ł̃v���[��唗�I����o�����Ă������ƂŁA�u�X�g���C�J�[�v�Ƃ��Ă̐���������ƍl���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�I�����Ă�̂́A�u�n�C�v���b�V���[�v�Ƃ������ł��B���K���������܂ŁA�u�v���X�̂����v�Ȃ��ł����A����ɒʂ���v���[��g�ɂ��邱�Ƃ��ł���B ����́A�v���[����{�l�����łȂ��A�`�[���S�̂��ӎ��������Ƃ�����ƍl���܂��B
�@ �g���Z���ł́A�����`�[������I�����ꂽ�I�肪�W�܂������邱�Ƃ��ł���̂ŁA����Ɂu�v���X�̂����v��������āA�u�v���X�̒��Œʂ���X�L���v�̏K����ڎw���Ă��܂��B �v���b�V���[�������Ă��ʂ���X�L���B������ӎ����ĂQ�O�O�X�N���g���[�j���O���Ă����܂��傤�B ���N���撣��܂��傤�B
�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə����Ċ����l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w���ɏ]�������������B �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə����Ċ����l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w���ɏ]�������������B
|
|
|
|
|
�����P�P�@�����̂��Ƃ͎����ŁE�E�E�Ɓ@�Ȃ� |
|
�@�Q�O�O�W�D�P�Q�D�Q�V�@
�@���̃R���������N�Ō�ɂȂ�܂��B��T�ԂɈ�x���e�������Ƃ�������A�����}�K�s����Ƃ������͎������g�̌o����m���̒I�����ɂ��Ȃ�܂��B�܂��A�N���u���[���h�J�b�v�⍂�Z�T�b�J�[�I�茠�A�i�V���i���g���Z���Ȃǎ����I�Șb��ɂ��ĐG��邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���āA�T�b�J�[���N�̊F����͓~�x�݂ł��ˁB �~�x�݂ɓ����đ��X�ɃN���X�}�X�ł������A�T�b�J�[���N�ւ̃v���[���g�͂Ȃ����̂ł��傤���B �T�b�J�[�V���[�Y�A�X�p�C�N�Ƃ��������O�����h�ŕ������܂����B�T�b�J�[�Q�[���Ƃ��������������܂����B�܂��A�T�����Ƃ��������������܂����B �撣���Ă���T�b�J�[���N�ɂ͂����������炵���v���[���g�����������Ƃł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�Ƃ���ŁA���̎����ł��̂ŁA�ЂƂӂ��b���ĉ������ˁB
�@�悢�T�b�J�[�I��ɂȂ邽�߂ɂ́A���K�����鎖�̑���͌����܂ł�����܂��A���̓~�x�݂Ƀ`�������W���ė~������������܂��B
�@����́A���̊Ǘ��Ǝ��ȊǗ��ł��B �d���\���ł����A�킩��₷�������u�����̎��͎����ł��悤�v�Ƃ������ł��B �T�b�J�[�V���[�Y���Ă��������A�������������ł���ˁB�����A���������܂���ˁB�ł��A�ڂ�ڂ�ɂȂ��ė����Ȃ��Ȃ�܂ŁA�������������邱�Ƃ��ł��Ă��܂����B
�@�܂�A���m���Ɉ����A����������Ƃ����������Ă��܂����B �v���ɂȂ�u�z�y�C���v���p��̎��������Ă���܂��B����́A�v��������ł��B
�@�A�}�`���A�̊F����́A�����̎��͎����ł��Ȃ���Ȃ�܂���B ���ꂪ�ł��Ȃ���A�v���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B
�@���ȊǗ��Ƃ͂ǂ��������Ƃł��傤���B �~�x�݂͂�����莞�Ԃ�����̂ł͂Ȃ��ł����B����Ȃ�A���Ԃ̎g�������������Ă݂܂��傤�B
�@ ���N���܂��A�����ɋN���܂����H���H�͉����ɁA�����ǂꂭ�炢�H�ׂ܂����B�ւ̏�Ԃ͂ǂ��ł����B�������v��I�Ɉ���ł��܂����B�W�����N�t�[�h�i�|�e�g�`�b�v�X��X�i�b�N�َq�Ȃǁj���H�ׂĂ��܂��B
�@�@�@�N���u�̗��K�̂ق��ɁA����I�Ƀg���[�j���O����v��������Ă��܂����B
�@�@�@�v��͎����ł����Ă��܂����B
�@�@�@�p�������ꂷ�鎞�Ԃ�����Ă��܂����B
�@�@�@�̂𐴌��ɕۂ��Ă��܂����B
�@�@�@�������ɂ͑��̎w�܂Ń`�F�b�N���Ă��܂����B
�@�@�@�X�g���b�`�ȂǁA�̂̃����e�i���X���s���Ă��܂����B
�@�@�@�A�Q���Ԃ����߂āA�悭����܂����B
�@���_�_�ł͂���܂����B�T�b�J�[���N�̓X�|�[�c�}���ł�����A�S�Ƒ̂��悢��Ԃɕۂ��́A���K�Ɠ������炢��Ȏ��ł��B �����̎����u��s�v�ł����Ă͑����܂���ˁB ������O�̂悤�ɏo���鎖����ł��B ��D���ȃT�b�J�[�𑱂��Ă����A�N�ɂ����������Ȃ��B ���������C����������A�Q�鎖�A�H�ׂ鎖�A�̂̎����A���̎��������鎖�͂炢���Ƃł͂Ȃ��͂��ł��B
�@�~�x�݂�ċx�݂͐��������ꂪ���Ȏ����ł��B���ɓ~�͑̒��Ǘ����o���Ă��Ȃ��ƕ��ׂ��Ђ�����A�H�ׂ����ŏ����s�ǂ��N�������Ƃ�����ł��傤�B ���邱�Ƃ��班�����撣���Ă݂Ă��������ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@ �Ƃ���ŁA���̌��e�������Ă��鎞�ɁA�t�B�M���A�X�P�[�g�̑S���{�I�茠���s���Ă��܂��B ���E�`�����s�I���̐�c�^���I����v���b�V���[�������Ă���悤�ł��ˁB ���́A��c�I��̃R�[�`�u�^�`�A�i�E�^���\���v����ɒ��ڂ��Ă��܂��B
�@
�@�`�����s�I�����[�J�[�ƌ����A�r��Í��I����w�������R�[�`�ł��ˁB �̐l�ł����A�G�f�B�^�E���[���g�Ƃ����{�N�V���O�̃R�[�`�����܂����B�ނ��A�`�����s�I�����[�J�[�Ƃ��āA�Ŋ��͈䉪�I��̃Z�R���h�����Ȃ��瑧���������܂����B ���E�ɂ͑f���炵���R�[�`�����̂悤�Ɍ��ʂ��o���Ă��܂��B �����錍������̂ł́H�ƌ������Ă��܂��B�I��̋C�����������o�����Ƃ�s������菜�����ƂȂǑ��⎎���ɗՂގ��̕��@�͒N�ł�����Ă��邱�Ƃł��傤�B
�@
�@�^���\���R�[�`�Ɛ�c�I��̃g���[�j���O�̗l�q�����āA���R�[�`�ɒʂ�����̂��Ċm�F���܂����B ����́u�����Ȃ������āA�����v�Ƃ������ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�{�N�V���O���X�P�[�g�������ăT�b�J�[���A�������Ƒ����Ă���Ɓu�ȁv�͕K�����܂��B �u�����ȁv���ǂ����̌��ɂ߁A�����āu�������v�B ����́A�{�N�V���O��X�P�[�g�̂悤�ȁA�R�[�`�ƑI��̂P�P�̊W������ł��邾�낤�B �������A�T�b�J�[�ɂ����Ă͂܂�̂ł��B �����A�o�ꂵ���������r�f�I�ɎB���Ă���̂ł���A���̓~�x�݂Ɍ��Ă��������B
�@�|�C���g�́A�{�[����D����V�[���ł��B
�{�[���������Ă��āA�U���Ɉڂ낤���Ă���V�[���ŒD�����ʂ����Ă��������B
�@�����̑I��͉E�����Ȃ̂ŁA���肪�E�ɂ��Ă��A���Ƀ{�[�������������Ȃ��ŁA�E���łȂ�Ƃ����悤�Ƃ��܂��B ���̏�ʂŃ{�[����D���Ă��܂��B �����A���̏�ʂō����A�܂�A���肩�牓�����̑��Ƀ{�[�������������Ă���A����̑����o�Ă��鎖���Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�Ƃ������ł��B
�@�������ɂ�����Ă��܂��B����́A�T�b�J�[���N�́u�����ȁv�ł��B ���Ƃ��Ȃ��Ă��܂���������̂ŁA�R�[�`����������Ȃ�������A�����Ȃ������肵�܂��B �ł��A�����Ă����Ď��R�ɒ�����̂ł͂���܂���B �R�[�`�Ɍ�����O�ɁA�����Œ����Ă݂܂��B ���肩�牓�����Ń{�[���������A�������g�����B ����́A���ʂɓ�����Ƃł͂���܂���B��肾����s���Ɉڂ��Ȃ������ł��ˁB
�@���̎�������~�x�݂̃e�[�}�ɂ��Ă��悢���炢�̑�ŁA���ʂ̂���e�[�}�ł��B �u�����ȁ�bad habit�v�ɂȂ�Ȃ������ɁA�������g����ugoog habit�v��g�ɂ��悤�B �N�����ɂ́A�V�c�t�A���Z�T�b�J�[�I�茠�E�E�E�y���݂ł��ˁB �悢�������}�����������I
�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə����Ċ����l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w���ɏ]�������������B �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə����Ċ����l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w���ɏ]�������������B
|
|
|
|
|
�����P�O�@�g���Z���Ō��邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂́H |
|
�Q�O�O�W�D�P�Q�D�P�W
�@�N���u���[���h�J�b�v�̃x�X�g�S���o�����A�Z�p�̍����Ə����ւ̃��`�x�[�V�����̍�����ڂ̓�����ɂ��Ă��܂��B �ǂ̃`�[�������I�ȃT�b�J�[��W�J���A�`�[����p�����ꂼ��ł��B
�@���̌��e�́A�������́uCF�p�`���[�J�@0-2�@���K�E�f�E�L�g�v�����Ă��珑���Ă��܂��B �L�g�̍U���̋N�_�ƂȂ��Ă���u�A���n���h���E�}���\�v�̃`�����X���C�N�łQ�_��D���܂����ˁB �L�g�̓o�`���[�J�Ƀp�X�����Ă��܂������A�n�[�t�E�F�C���Ă���̏c�p�X�͌����ɃJ�b�g���Ă��܂����B DF�������̂ŁA�}���\�{�Q�C�R�l�ł̍U���ŏ��Ȃ��`�����X�����m�ɂł���Ƃ����Q�[���ł��ˁB
�@�p�`���[�J���A�V���[�g�p�X���Ȃ��|�[�b�V�����T�b�J�[���X�O�������郌�x�����f���炵�����̂ł����B �|�[�b�V�������������̂ŁA�V���[�g�`�����X������܂����A���S�ɕ����ăV���[�g���Ă����ʂ͂킸���ł����B
�@ �����I�҂̃L�g�̃f�t�F���X�\�͂̍����������܂����B ���ꂼ��̃`�[���J���[���o���A���Ɋy���������ł����ˁB ���{�}���`�F�X�^�[�t��́A�܂����Ă��܂���B�y���݂ł��B
�@�N���u���[���h�J�b�v�̃x�X�g�S�ɏo�ꂵ�Ă���I�肪�A�K�������ꍑ�̂v�J�b�v��\�ł��邩�Ƃ����Ƃ����ł͂���܂���B�L�g�̃}���\���A���[���`���̑I��ł����A��\�ɓ����Ă��܂���B �A���[���`���̑w�̌�������Ă���Ƃ������ɂȂ�ł��傤�B �@�@�K���o���́A���{��\�I��́A�����A���c�A���{���������܂��B��\�ł̎厲�̂ЂƂ�Ƃ��ĉ����̑��݂͑傫���ł��ˁB��\�ł��A�K���o�ł��u�p�X�T�b�J�[�v��W�J���A��a���̖����v���[�����Ă���ƌ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@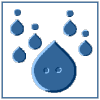
�@�@���N���u�`�[���ƃg���Z���̈Ⴂ
�@�W���j�A���烆�[�X�N��ɂ����āA�����N���u�͂ǂ�ȃT�b�J�[�����Ă���ł��傤���B �琬�N��Ƃ���������A�h���u����̂̃`�[���Ń{�[������������ǂ��ł��܂��h���u������B�h���u���Ƃ����l�Z�p��O��I�Ɉ琬����B���������N���u������ł��傤�B
�@����A�p�X�T�b�J�[�����Ƃ����N���u�ł́A�V���[�g�p�X����̂Ƀ|�[�b�V�������鎖���e�[�}�ɂ��Ă���N���u������ł��傤�B�܂��A�g�̔\�͂̍����I��i���������A�w�������j��Ƃ���`�[���ł́A�����O�{�[����̂ɋ�ŏ������Ă���`�[��������܂��B�e�N���u�`�[���̖ڎw���T�b�J�[�ƑI��̌��ɂ���āA�N���u�`�[�����킢�A�܂��A�琬���Ă���ƌ����܂��B
�@����̃N���u���[���h�J�b�v�����Ă��Ă��A�N���u�̐�p�Ƒ�\�̐�p������Ă��Ă��A��\�I�肽���͂�������Ή��ł��Ă���Ƃ����_�����ė~�����Ǝv���܂��B �N���u�ł́A�X�g�b�p�[�����Ă��邩��A�g���Z���`�[���ł̓T�C�h�����Ȃ��Ƃ��A���Ղ����Ȃ��B ����ł́A�܂����킯�ł��B �N���u�ł́A�g�b�v��������Ă���̂ŁA�T�C�h�o�b�N�͂��Ȃ��B������܂����킯�ł��B
�@�g���Z���`�[���Ƃ��ĕs���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��āA�琬�N��ł��鏬�w�����璆�w���ł���A�ǂ̃|�W�V������^�����Ă��A���̃|�W�V���������Ȃ��ė~�������A���ꂪ�v������Ă���ƌ����܂��B �N���u�ł́A�Ȃ��Ȃ����낢��ȃ|�W�V�������o�����邱�Ƃ͓�������m��܂���B �ł��A�^����ꂽ�|�W�V�����ȊO�ɂ��ăC���[�W���邱�Ƃ͏o����͂��ł��B
�@���Ȃ��i�I��j���t�H���[�h�ł��낤���A�{�����`�ł��낤���A�Z���^�[�o�b�N�ł��낤���A���肪�����Ă���{�[���͒D���ɍs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A���Ԃ��D���ɍs���Ă�����A����I����}�[�N���Ȃ���Ȃ�܂���B �܂��A�`�[�����{�[���������Ă��鎞�ɂ͂ǂ̃|�W�V�����ł����Ă��A�T�|�[�g���K�v�ł��B�Z���^�[�o�b�N�̓t�H���[�h���{�[���������Ă��鎞�͋x��ł������R�͂���܂���B�T�|�[�g�ł���ꏊ���K������̂ŁA���������K�v�ł��B
�@���̂悤�ɁA�U��̊�{�⌴�����g�ɂ��Ă���A�g���Z���`�[���łǂ̃|�W�V������^�����Ă��A������͂��ł��B �t�ɁA�o���̖����|�W�V���������ǂ�ǂ�g���C���Ă����ė~�����ł��ˁB���������h�����T�b�J�[�I��Ƃ��Ă̔\�̓A�b�v�ɂȂ���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@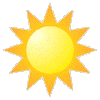
���N���u�̃T�b�J�[�ƃg���Z���T�b�J�[ �g���Z���ł́A���l�ȋZ�p�����߂Ă����܂��B
�@����Ă邱�Ƃ��e�[�}�ɏグ�Ă��܂����A���Ƃ��h���u���͒N�ɂ����������Ȃ�����ǁA�Q�O���̃p�X�����m�ɏR��Ȃ��I��́A�T�b�J�[�I��Ƃ��Đ�������ł��傤���B�Ƃ������ł��B �Q�O���̃p�X�𐳊m�ɏR���{���x���������Ă��邯��ǁA�����ăh���u���œ˔j����B
�@�܂�I�����������ăv���[���鎖���o����Ƃ������݂������ė~�����Ƃ������ł��B ��������N���u���h���u����̂̃`�[��������A�p�X���K�����Ȃ��ƍl����Ȃ�A�p�X�̗��K���l���x���ōs���K�v������܂��B �N���u�́A�g���Z���I����o�����߂ɂ���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������𗝉����Ă��������B�t�ɁA�g���Z���̓N���u�ɑ��āA���������T�b�J�[�������Ă��������A�����łȂ��ƃg���Z���ł͒ʗp���܂���A�Ƃ����������蓾�܂���B
�@�g���Z���ɗ���Ƃ������́u�v�Ƃ��Ă̕]���ł��B���������Ⴂ���Ȃ��ŗ~�����ł��B �N���u�Ŏ厲�̑I�肪�g���Z���ł��厲�ƂȂ�邩�Ƃ����ƁA�厲������W�߂�킯�ł����炠��Ӗ��u�����v�̐��E���g���Z���ł��B���̒��Ŏ厲�ɂȂ�A�Ȃ�Ȃ��́A�l�Ƃ��ăv���[�̈����o���̑�����A���̃��x�����ǂꂾ���������̂������Ă��邩�B�����ɂ������Ă���ł��傤�B
�@�g���Z���`�[���ŁA�u�����̓V���[�g�p�X���Ȃ��Ń|�[�b�V��������T�b�J�[�����Ă݂悤�v�Ƃ����e�[�}�̎��ɁA�����O�L�b�N�����ӂ�����ƌ����āA�{�[�����������瑊��f�t�F���X�̗��Ƀ{�[������荞��ł�����ǂ��ł��傤���B�L�b�N�͂���Ȃ��ƕ]�������ł��傤���B�������܂��ˁB�|�[�b�V��������������Ă��Ȃ��Ƃ����]���ɂȂ�Ȃ��ł��傤���B
�@�܂��A�h���u�������ӂ�����ƌ����āA�悢�|�W�V�����ɂ��钇�Ԃւ̃p�X�����h���u����D�悳���Ă�����A���̏�ʂł̔��f�Ƃ��Ă͂ǂ��ł��傤���B�h���u�������܂��A�Ƃ����]�������u���肪�����Ă��Ȃ��v�ƕ]������Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@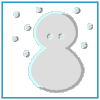
�@�@�@�@�@�@���Ӑ}�������ăv���[���悤�B
�@ �`�[���ł̓Z���^�[�o�b�N������Ă���̂ŁA����̂P�P�Ƃ����ΐl�v���[�ł͎��M�����邯��ǁA�D�����{�[���͂����傫���N���A���Ă��܂��I�肪����Ƃ��܂��B ���̑I�肪�g���Z�����Ԃɂ��������܂����u�N���A�����瑊��ɒ��˕Ԃ���Ă��܂�����Ȃ����A�l�������ŃT�|�[�g���Ă����̂ɉ��œn���Ă���Ȃ������v
�@�����Ŕ��f���ė~�����̂ł��B�u�{�[����D������܂��N���A���낤�v�ƌ����̂��A�u�N�ɓn���Ă��A���肪����ė��Ă����̂ŃN���A���ăs���`���������v�ƌ�����̂��B �܂�����I��́A���R�G���A�Ńh���u�����J�n�����Ƃ��܂��B���̒��Ԃɑ��āu����̖��������Ȃ��̂ɁA���Ńh���u�����Ă���B���U���낤�B�p�X���Ă���v�Ƃ����I�肪���܂����B
�@�ǂ������܂����B
�@�u�N���u�ł́A�{�[������������܂��h���u���Ƌ�����Ă���v�ƌ����̂��A�u����̖��������Ȃ��̂͂킩���Ă����A������A�h���u���Œ��Ղ̑�����������āA�T�C�h�`�F���W�����悤�Ǝv�����v�ƌ����̂��B �N���u�ł���Ă���v���[����������g�ɂ�����A�ǂ�ȏ�ʂłǂ̂悤�ȃv���[�����鎖���A�`�[����p�ɂȂ�̂��B
�@�Ӑ}�������ăv���[����B�Ӑ}�������Ĕ��f����B
�@���f�������ɂ��āA���̈Ӑ}��b�����Ƃ��ł���B���Ƃ����ʂ��~�X�ɏI������Ƃ��Ă��A�Ӑ}�̂���v���[�ł̎��s�́A���̐����ɂȂ���܂��B
�@�Ӑ}�̂Ȃ��v���[�̐����⎸�s�͒P�Ȃ���R�ł��B
�@���̂悤�ȈӐ}�̂���T�b�J�[���A��l�ɂȂ�Ȃ��Əo���Ȃ��̂ł��傤���B �������A�g���[�j���O����ł́A�R�N����S�N���ł���������ƈӐ}���������v���[���ł��܂��B �@���̂��߂ɂ́A�u�����Ŕ��f����v���̊�b��A�u���f�ɉ����ē������̂ł���A�W���e�B��X�L���v�����̔N��̃��x���ɍ��킹�Đg�ɂ��鎖���K�v�ł��B
�@ ���̃R���������ł��邨������A���ꂳ�A���q����̃Q�[�����ς�@���������A�ƂɋA���Ă���A���q����ɕ����Ă݂Ă��������B
�@�u�P������S�[���O�Ńt���[����������ǁA�ǂ����ăh���u�������́H�v
�u�����������������v�Ȃ̂��u�����Ă���p�X���悤�Ǝv�����v�̂��u�C�����Ȃ������v�̂��B
�@�����������������邩������܂����B
�@�u�P�������ׂ̗̃f�t�F���X����������A�P�������Ƀp�X���Ă��Ƃ���Ƃ�����������v
�@�@�Ǘ��u���O�u�e�q�̂��߂̃W���j�A�T�b�J�[�R�[�`���O�v�ł́A���̂悤�Ȑe���ւ���R�[�`���O�ɂ��ďЉ�Ă��܂��B�K�₵�Ă��������ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ http://jr-soccer-coaching.naotech.info/
�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə����Ċ����l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w���ɏ]�������������B �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə����Ċ����l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w���ɏ]�������������B
|
|
|
|
|
�����X�@�U��������@���N��N��U��Ԃ��āI�I�@ |
|
�@�Q�O�O�W�D�P�Q�D�P�O
�@���N�T�b�J�[�E�ł́A�N���u�P�ʂ̑������������āA���݂̓g���Z���`�[���̑�
�s�Ȃ��Ă��܂��B�g���Z���ɑI�����ꂽ�I��͎����̗͂������@��Ȃ̂ŁA���C�ǂ�
�v�����ăv���[���Ă��������ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�@�I�����ꂽ�I����A�I������Ȃ������I����A���̎����ɁA���N��N��U��Ԃ��Ă݂�
�͂ǂ��ł��傤���B
�@�܂��A�`�[���̐��т����A�l�Ƃ��Ẵv���[��U��Ԃ��Ă݂܂��傤�B
�@�܂��A�U���ł��B���̂������ɂ��āA�U��Ԃ��Ă݂Ă��������B
�@�@�E�������������ςĔ��f����v���[���鎖�B
�@�@�E�S�[����D���Ƃ����ӎ��Ńv���[���鎖�B
�@�@�E�����Ă���{�[���ɑ��Ă��₭����Ă����āA�����Ȃ���R���g���[�����鎖�B �@
�@�@�E�����^�b�`�ł̃{�[���R���g���[�����鎖�B
�@�@�E�{�[������O�ɂ�������ςĂ����āA
�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ̂悤�ȃp�X���o���悢���悢�I�������鎖�B
�@�@�E�|�[�b�V�����A�˔j�ȂǁA�ɉ������p�X���o�����B
�@�@�E�p�X�����鎞�́A�O���E���_�[�̑����p�X�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�������ł̃p�X�Ȃǃp�X�̎���ς��鎖�B
�@�@�E�{�[���������Ă��Ȃ��ŁA�|�[�b�V�����̈ʒu�֓����̂��A
�@�@�@�@�@�@�@�@�˔j����ʒu�֓����̂����f��ς��Ă������B
�@�@�E�₦���A�{�[���ɑ��Ċւ�葱���鎖�B
�@�@
�@���̂悤�ɁA�U���������Ƃ��Ă݂Ă��A�₦������������{�[���̈ʒu�ɉ����āA����
�̈ʒu�ɉ����āA�ւ�葱���鎖���K�v�ɂȂ�܂��B
�@�ǂ��ł��傤���A���̂悤�ȃv���[���o�����ł��傤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@ ���Ɏ���ł��B
�@�@�E ����ň�ԑ�Ȏ��̓|�W�V���j���O���ӎ����ăv���[�����鎖�B
�@�@�E ����̃{�[���ɑ��ϋɓI�ɃA�v���[�`�������čs�����B
�@�@�E�܂��A�`�������W���鎞�̗D�揇�ʂ��l���Ȃ���|�W�V�������C�����鎖�B
�@�@�E�`�������W�A���h�J�o�[��₦�������Ă������B
�@�@�E�{�[����D��ꂽ�u�ԂɎ���ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���₢��ւ��Ń{�[�������ɍs�����B
�@�@�E����ւ̃v���b�V���[�����������鎖�B
�@ �ǂ��ł��傤���A���̂悤�ȃv���[�����N�͏o�����ł��傤���B
�@�U�������ɂ�����l�̃v���[�̎���ǂ����Ă������߂ɂ͂ǂ�����悢���B ����
�܂ł̐����̂悤�ɁA���������鎖���K�v�ł��邱�Ƃ͂����܂ł�����܂���B
�@ ���������鎖���ł��܂������B
�@�܂�A�����~�߂��ɑ��葱���鎖���o���܂������B
�u����v��������O�Ɋ�������悤�ɂȂ邽�߂ɂ́A���K���ɂ������~�߂Ȃ����ł��B
�`�[���ł̗��K���ԓ��Ɂu����g���[�j���O�v����邱�Ƃ͌����I�Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA��
��g���[�j���O�����l�Ńg���[�j���O������̂ƌ����܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�@���̎����A���肱�݂����Ă͂ǂ��ł����B ���邱�Ƃ���łȂ��Ȃ�ƁA�v���[�ɂ��傫�Ȍ�
�ʂ����܂�܂��B �܂��A�U���ł́A�T�|�[�g���ϋɓI�ɂł���悤�ɂȂ�A���r���[�Ȋp
�x�ł��炤�̂ł͂Ȃ��A�������͂�����������A�c�֔�����Ƃ��͂������葖��ʂ���Ƃ���
�����J��Ԃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B
�@�����Ď���ł��B �{�[����D���āA�ǂ������ĒD���ɍs���Ƃ�������͂ƂĂ��炢��
�̂�����܂��B�ł��A���̂悤�ȑ���ő���Ƀv���b�V���[��^���鎖�̂ł���I�肪�u��
���I��v�ƌ�����̂ł��B ���鎖����łȂ��Ȃ�A���M�����Ă���ƁA����ɂ����Ă���
��������v���[�̏�ʂ������Ȃ�܂��B
�@���R�A�{�[����D���Ă���U���Ɉڂ鎞�����葱���邱�ƂɂȂ�܂����A�s���`����`��
���X�ގ����o���܂��B
�@�n���Ȏ��ł����A�g���Z���̂悤�ȑI�����ꂽ�I��B�̒��ł��A���葱����I��́A�a��
�ڗ����Ă��܂��B �{�[�������������ɔh��ɖڗ����Ƒ��葱����v���[�ŏa���ڗ���
���́A�]���͓������ƍl���܂��B
�@���̂悤�ȃv���[�����邽�߂ɂ́A�S�̎���������Ȃ̂ŁA�����n�[�g������������
�������ł����Ə������J����鎖�ł��傤�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�@�����^�c������u���O�ɂ��t�B�W�J���g���[�j���O����^���ɂ��ď����Ă���̂ł�
�ЖK�₵�Ă��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ http://jr-soccer-coaching.naotech.info/
�@���̓x�A�߂ł����������ꂽ����I��Ȃǂ́A�a���ڗ����Ă���I��̈�l�ƌ�����
���B�t�@���̈�l�Ƃ��đ�ς��ꂵ���v���܂��B
�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K�� �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��
�]�v�Ə����ĊǗ��l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[����
���܂��̂ł��̎w���ɏ]���Ă��������B
|
|
|
|
|
|
�����W�@�悢�~�X����������d�˂悤�I |
|
�Q�O�O�W�D�P�Q�D�S�@
�@�悢�~�X����������d�˂悤�I
������~�X�������ă~�X����킯�ł͂���܂����ˁB������M���ăv���[�������ʂ̃~�X�B����͎�
���ł��u�~�X�v�����Ƃ킩��܂��B �u���͐��������悤�v�Ƃ����C�����ɂȂ�܂���ˁB ����́u�ϋɓI
�Ƀv���[�������ʂ̃~�X�v�Ȃ̂ŁA�悢���s�ƌ����܂��B
�@���̂悤�ȁu�悢���s�v�Ɓu�����̌��v�𐔑����d�˂Đ������Ă����ƍl���܂��B �ł�����A���s�ɂ�
�u�悢���s�ƈ������s�v������܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�@ ����́A�I�����ꂽ�g���Z���I��ɂ������邱�Ƃł��B �u�I�����ꂽ����~�X���Ă͂����Ȃ��v ��
�������l���������Ă���I����������邱�Ƃ�����܂��B �ӎ��������ł��B �R�[�`�B�́u�悢���s��
�������s���v���悭���Ă��܂���B �������Ȃ���Ύ��s�����蓾�Ȃ��̂ŁA����������������g���C��
�邱�Ƃł��B ���s����͂��̌��ʂł��B
�@
�@���s�ɂ��悢���s�ƈ������s������ƌ�������ǂ���͂ǂ�Ȃ��́H
�@���s�͎��s�ł�����A�悢���������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B �����������ӌ�������Ǝv���܂��B �T�b�J
�[�ɂ͎��s�͕t�����ł��B �悭�Ȃ����s�Ƃ́u���ɓI�ȃv���[�ɂ��~�X�v���ƌ����܂��ˁB
�@
�@��قǂ̗�Ō����A�V���[�g�`�����X������ǁu�������O���Ɛӂ߂��邩��p�X���悤�v �u���M
���Ȃ����疡���Ƀp�X���悤�v�u�A�V�X�g���J�b�R�C�C����p�X���悤�v �����������z����p�X���Ă�����
���]�߂Ȃ��ł��傤�B �~�X���鎖�̓T�b�J�[�̖{���ł�����܂��B �~�X������Ă��Ă̓T�b�J�[���o
���Ȃ��Ƃ������ł��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�@����̓R�[�`����u�~�X������Ȃ��Ńv���[���悤�v�Ƃ悭�����Ă���̂ł킩��₷���Ǝv����
���B �ł��A���K�ł͂ǂ��ł��傤���B�~�X���Ă����C�ɂȂ��Ă��Ă͗��K���ʂ��オ��ł��傤���B �~
�X�ɕ��C�ɂȂ��Ă͂����܂��A���K�ł��u�悢�~�X�v�����Ăق������̂ł��B �����ǂ��~�X�ŁA��
���ǂ��Ȃ��~�X���킩��܂����B
�@ �Ⴆ�A�t�@�[�X�g�^�b�`�ő���̎��Ȃ��Ƃ���Ƀ{�[����u�����K������Ƃ��܂��B �����̏�
���A�{�[�����Ă���t�@�[�X�g�^�b�`���������Ȃ肪���ł��B ����͂悭�Ȃ��~�X�ł��B ����Ɏ�
���Ȃ��A���������Ƀ^�b�`���悤�Ƃ�����X�s�[�h���K�v���A�Ƃ����X�y�[�X�ւ̎����o���� �v����
���đ傫�����邮�炢�̃^�b�`�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@
�@�ł�����A�悢�~�X�Ƃ́u������Ƌ������ȁA�������ȁv�Ƃ����^�b�`�B �����^�b�`�Ƃ́A����Ɏ���
��̂��|������A���̃^�b�`�Ŏ������^�b�`���₷���߂��ꏊ�փR���g���[�����邱�ƁB �������^�b
�`�ł��Ă��A����ɒD���`�����X�������ɗ^���Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ�܂��B
�@���̂悤�ɁA�������悢�~�X�Ȃ̂������~�X�Ȃ̂��C�����Ȃ��ƃ\���ł��ˁB
�@ �R�[���𗧂Ăăh���u�����K������ꍇ�ł��A�R�[���ɓ��Ăĕ��C�ɂȂ�Ȃ������K�v�ł����A �R
�[���ɓ��Ă鎖��^�b�`�~�X������邠�܂�A�S�R�X�s�[�h�A�b�v�o���Ȃ������悭����܂���B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�@�~�X���邩���m��Ȃ�����ǁA�`�������W���悤�B
���ꂮ�炢�̋C�����ŗ��K�ɂ̂��ގ�����ł��B
�@���̂��߂ɂ́A��������C���[�W�������Ƃ���ł����A����̃R�����ɂāB
�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə��� �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə���
�ĊǗ��l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w��
�ɏ]���Ă��������B
|
|
|
|
|
|
no7 �@���̃e�N�j�b�N�͉��̂��߁H |
|
�Q�O�O�W�C�P�P�C�Q�U
�@���̃e�N�j�b�N�͉��̂��߁H
�P���̃W���K�A���t�e�B���O�A�t�F�C���g�͉��̂��߂ł��傤���B
�߂����t�@���^�W�X�^�Ń{�[���R���g���[����g�̂��Ȃ���g�ɂ���͉̂��̂��߂ł��傤���B
�N�[�o�[���\�b�h�Ń{�[���}�X�^���[��g�ɂ���͉̂��̂��߂ł��傤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�ǎ҂̊F����₨�q����͂��Ƃ��ЂƂ�ł��R�c�R�c�Ɨ��K�𑱂��āA�悢�{�[���^�b�`��g�ɂ�
�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �ŋ߂̏��N�T�b�J�[��[�X�A���Z�T�b�J�[�����Ă��{���ɃX�L
�����A�b�v���Ă���Ǝv���܂��B
�@�R�O���̃N���X�{�[���������^�b�`�ŃR���g���[��������A��������c�[�p�X�œ˔j����V�[������
�Ă���Ƒf���炵���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@ �{�[�����S�̃g���[�j���O�����Ă������ʂ��o�Ă���̂ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�P���ƗV���̂��Ƃ��v���o���܂����B
�@���t�e�B���O����q���ɋ߂Â��āA�������邮����Ƃ������̂ł��B
���̎q�͋C���U�����̂��A�W�����������̂��~�X���ė����Ă��܂��܂����B
�u���肪���Ă��A����ɂЂ��ς��ĕ��C�ɂȂ낤�v
�@�����A�P���͌����܂����B
�@ �P���̃e�N�j�b�N���A�߂����t�@���^�W�X�^���A�N�[�o�[�̃{�[���}�X�^���[���u���肪���Ă��g����
�X�L���v��ڎw���Ă��܂��B
�@���q���ЂƂ�Ń{�[���^�b�`�̗��K�����Ă���Ƃ��ɁA�����A���K�̎�`��������Ȃ�A�u����
�܁v�����Ă����ĉ������B
�@�W���K��h���u���̗��K�ŁA�R�[����ɂ��鎖�ƁA�l�Ԃ�ɂ�����K�̌��ʂ͑S���Ⴂ��
����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�N���u�̂�����̗��K���j���[�ł��B
�@���̓��̃e�[�}�̓t�@�[�X�g�^�b�`�ł����B
�@
�@�}�[�J�[�Ŗ�R���l���O���b�h�����܂��B�P�O�������Ă�������܂��B ���ꂼ��̃O���b�h�ɑI
�肪����A�O���b�h���Ń{�[�����āA�O���b�h���烏���^�b�`�Ŕ����o�ĂāA���̃^�b�`�ŁA��P�O
�����ꂽ�O���b�h�̑���Ƀp�X�����܂��B
�@
�@�V���v���ȗ��K�ł��B�e�q�ł��ł��܂��ˁB �m�[�v���b�V���[�ł͖{���ɏ��ɂł��܂��B ������
�y���v���b�V���[�������܂��B �O���b�h�ƃO���b�h�̊ԂɃv���X��������I�肪�����āA�{�[�����p�X
���ꂽ�u�ԂɎ�ɃA�v���[�`���܂��B
�@�O���b�h�ɓ����Ď��Ƃ���܂ł͂��Ȃ��̂ł����A�^�b�`������đ傫���Ȃ�܂��ˁB ���������
�������Ă���Ɓu���ɗ��Ȃ�������v���v�Ɗ���Ă��Ă��܂��܂��B �����ŁA�u���ɍs���悤�Ɂv��
�܂��B�O���b�h�ɓ����ă{�[����D�����ł��B��قǂ�苭���v���b�V���[�ł��B �܂��A�~�X������悤
�ɂȂ�܂��B ����������Ă����ƃ~�X�����Ȃ��Ȃ�܂��B
�@���̂悤�ɁA�g���[�j���O�́u����v�����āA������ɋ߂��`�ōs�����Ƃ����ʓI���ƌ����Ă�
�܂��B �ł��A�ŏ��́u�m�[�v���b�V���[�v�ł̃{�[���^�b�`���o���Ȃ���v���b�V���[�L�̏�ԂŃR
���g���[�����o���Ȃ��ł���ˁB
�@����ɁA�m�[�v���b�V���[�łP�O�O���ł���悤�ɂȂ��Ă���A�v���b�V���[������Ƃ����ꍇ�A���P
�O�O���ɂȂ�̂��H�Ƃ������x���������Ȃ��ł��傤�B
�@�U�O�����x�̐��x�Ńm�[�v���b�V���[�łł���A�v���b�V���[�̒��Ńg���[�j���O���Ă��悢�ł���
���B
�@�R�O���̐��x�ł́A�v���b�V���[��^���Ă��قƂ�Ǘ��K���ʂ�����܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@ �@ �@
�@���ׂẴX�L���́u����̃v���X�̒��Ŏg���邱�Ɓv���ڕW�ł��B������u�I�[�v���X�L���v�ƌ�����
���B �m�[�v���b�V���[�́u�N���[�Y�h�X�L���v�ƌ����܂��B�R�[�`���O�p��ł��B
�@
�@ �����������̓R�[�`�������m���Ă���悢���Ƃł͂Ȃ��āA�ǎ҂̊F������g�߂ȗ�ɒu������
�čl���Ă���������Η������Ă���������Ǝv���܂��B
�@���Ƃ��A�싅���N�B �f�U������܂��B�f�U������Ȃ��Ńv���ɂȂ����I��͂��Ȃ��ł��傤�B ��
���A�L���b�`�{�[���B��������Ȃ��Ńv���ɂȂ����I������Ȃ��ł��傤�B
�@�T�b�J�[�ł͂ǂ��ł��傤���B���t�e�B���O���炢�ł��傤���B�W���K�X�e�b�v�Ȃǂ�����܂��ˁB ����
�ł̓N���[�Y�h�X�L����O��I�ɂ���Ă����A���K�̂�����͑���̂��钆�Ńg���C����B
�@
�@�o�b�g�̑f�U��̓{�[����ł��߂̃g���[�j���O�ł��ˁB �ł́A���t�e�B���O�͉��̂��߂̗��K
�ł��傤���B �����Ń��t�e�B���O�������ʂ͂���܂���B�ł����ł��̂ł��傤�B �싅�ł̓{�[��
��łƂ��ז������鑊��͂��܂���B�{�[�����L���b�`���鎞�Ɏז������鑊��͂��܂���B
�@�T�b�J�[�̓{�[�������Ƒ��肪�W�܂�悤�ɂł��Ă���X�|�[�c�ł��B ���肪���Ă���ĂāA��
���Ƀ{�[�����킽���Ă�����܂�Łu���e�Q�[���v�ł��B �{�[���������Ă��Q�ĂȂ����ƁB ���̂���
�ɂ̓{�[���𑫂ň������ƂɎ��M�����K�v������܂��B
�@���̂��߂̃��t�e�B���O�ł��B �{�f�B�o�����X���悭�Ȃ�����A�X�e�b�v���[�N���悭�Ȃ�����A���t�e
�B���O�̌��ʂ͏��Ȃ��Ȃ��ł��B �ł�����A�C���X�e�b�v�ł����t�e�B���O���P�O�O�O���
�ł���A���̎��Ԃ������Ƃ��܂��g���܂��傤�B �C���T�C�h�A�A�E�g�T�C�h�A�q�[���A���A���A�ȂǁA��
�ȊO�̕��������ׂĎg���B��������E���݂ɂ����B
�@��������P�O�O�O��ł���I����A�A���E���U���[���h�T�ł���I��̕����\�����L
����܂��B �{�[���ւ̑Ή��\�͂����܂�A����ɒD���ɂ����Ȃ�܂��B
�@�܂�A���M�����܂��B
�@���������̗��K�ł��B�����̗��K��A�E�g�T�C�h��C���T�C�h�̃��t�e�B���O�Ȃǁu�ł��Ȃ��v��
����Ȃ��Ń��b�c�g���C�ł��B���ΕK���ł���悤�ɂȂ�܂��B
�@ �e�́A�͂��܂��Ă����Ă��������ˁB
�@�ł���悤�ɂȂ�����A�u�v���b�V���[�v�������Ă����Ă��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@ �����r��I�藦����Z���e�B�b�N�͂b�k�̃O���[�v�\�I�Ŕs�ނ��Ă��܂��܂������A�{�[��������
�čQ�Ă����������Ƃ��Ȃ��ł���ˁB���M�����Ղ�̊�ł��B ���M�͊��p�Ɍ���܂��B���M��
�Ȃ��������ƁA����Ɋ��ă{�[�������ĂȂ��Ȃ�܂���B
�@�u�{�[�������Ă�ȁA�����́v�Ƃ�������v�킹��A����͎��ɂ��Ȃ����̂ł��B
�{�[���ɑ��鎩�M�B
�@�@����͑��肪���Ă��A�ǂ�ȏł����������邱�ƁB ���b�c�g���C�I
�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə����� �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə�����
�Ǘ��l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w����
�]�����������B
|
|
|
|
|
|
�����U�@�@���{��\��ƍ��Z�T�b�J�[�ƃg���[�j���O�@ |
|
�Q�O�O�W�C�P�P�C�Q�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���{��\��@��
�@
�@�m�`�a�n�ł��B�Q�s���ł��B
�@���T�̃R�����́A�v�t�\�I�̃J�^�[����܂ŗ��������Ȃ��̂ƍ��Z�T�b�J�[�I�茠�̑g�ݍ���
�����C�ɂȂ��āA�����x���Ȃ��Ă��܂��܂����B
�@
�@19���[��̃e���r�����͂����ɂȂ�܂����ˁB�J�^�[����͂R�|�O�ŏ����܂����ˁB�������Ȃ�
�ƁA�A�E�F�[�ł̏��_�R�Ɩ����_�͌��ʂƂ��Ă͏�o���ł��B
�@���z�͂������ł����B�c���A�ʓc�A��仉��I�肪���߂Ă���܂������A����͂͑f���炵����
���B
�@�J�^�[���f�t�F���X������āA�`�����X��������̂́A�����r��I��≓���I�肾���ł͂����
����ł����B ���́A���J���I��i�E�H���t�X�u���N�j�������ƌ��Ă��܂����B�`�����X�ɗ���ł���
�����ˁB���ɂ������������Ă��܂����B
�@�C�O�ł̌o���Ȃ̂��A�Q�[���̓ǂݕ������ɂ��炵���ł��B�E�H���t�X�u���N�ł��ŋ߃g�b�v
�����o�������Ƃ�����������A�c�ւ̓������ǂ������ł��ˁB�J�^�[���̃f�t�F���X���������āA
�g�b�v�̂R�l�ɃX�y�[�X��^���Ă��܂����ˁB
�@���̕��A�����r��I��͎��������V�[��������܂������A��͂�Q�[���������Ă��܂��B
�@�O��̃V���A����ςāA�J�^�[����Ɍ������ē�����̂��Ȃ��Ȃ��ƐS�z���Ă��܂������A�C�O
�g�͋Z�p�����łȂ��A���_�I�ɂ��A�Q�[���̓ǂݕ��������g�Ƃ̍����������Ă��܂����B �C�O
���[�O�Őg�ɂ�����̂́A�v���[�̂��܂������łȂ��u�T�b�J�[�Ƃ����Q�[���̐킢���v�Ȃ�ł�
�ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���Z�T�b�J�[�@��
�@���āA���Z�T�b�J�[�I�茠�̓s���{����\�Z�����肵�A�������ڂ��Ă����F���Z�����ꌧ��
�\�ɂȂ�܂����B��W�V��S�����Z�T�b�J�[�I�茠���́A�P�V���ɑg�ݍ��킹���I���s���܂�
���B�s���D���A���}���A�������鐼�A��z�ȂǑS�S�W�Z���A���N�̂P���P�Q���̌������ڎw����
�킢�܂��B
�@�ڂ����͑�87�Z�T�b�J�[�I�茠�̂g�o���������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://www.ntv.co.jp/soc/
�@�O��̃R�����ł́A���E�̂P�W�̓r�b�O�N���u�Ŋ��A�v�t��ڎw���Ă���Ə����܂������A
�C�O���[�O�ł͂P�V��P�W�̑I��B�����S�[�����グ��Ƃ����j���[�X���ǂ�ǂ��э����
���܂��B
�@�|�W�V�������ǂ��ł����Ă��A�S�[����_���Ƃ����u�T�b�J�[�̖{���v���g�ɂ��Ă���Ȃ���
�����Ă��܂��B
�@ ���Z�T�b�J�[�I�茠�́A�i���[�O�ւ̔��Ƃ����C���[�W������܂����A�i���[�O�����g�D�̃��[�X
�`�[���̑I�肽��������̏�͈Ⴂ�܂����A�撣���Ă��܂��B
�@���T���̃����}�K�ɂ́A����Ȃi���[�O��ڎw�����N�B�ɓǂ�ŗ~�����{������̂ŏЉ�܂�
�ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�@
�@�@�@�@�@�@���@�g���[�j���O���@�Љ�@�@�u�l�s�l���\�b�h�v�Ƃ́@��
�@���̂g�o�̓ǎ҂���A�ǂ�ȃg���[�j���O����������̂��Ƃ悭������܂��B����́A�ЂƂ��
���K������@�łȂ��A�F����������N���u�̗��K�ňӎ����Ď��g�ނ��ƂŌ��ʂ��Ⴄ��A�Ƃ�
���b�����܂��B
�@ �R�[�`����郁�j���[��w�����@���ǂ�ȈӖ������̂��H
�����m���Ă���A���K������Ɍ��ʂ������Ƃ������ł��B
�@�u�l�s�l���\�b�h�v�@�m���Ă�����������Ǝv���܂��B
�@�@�@�@
�@�@�@�@�l�̓}�b�`�A�܂�Q�[����~�j�Q�[���ł��ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�s�̓g���[�j���O��h�����ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ЂƂ̂l���}�b�`�ł��B
�@�}�b�`���āA�g���[�j���O���āA�}�b�`����@�Ƃ������̂ł��B
�@
�@�ŏ��̃}�b�`�ł́A���̓��̃g���[�j���O�e�[�}�ɍ��킹�āA���ڂ���|�C���g���w�����܂��B
���Ƃ��A���̓��̃e�[�}���u�J�o�[�����O�v���Ƃ��܂��B
�@�ŏ��̃Q�[���ŁA�J�o�[�����O�����𒍖ڂ��܂��B�i�t�H�[�J�X����Ƃ����܂��j �S�[�����O������
�h���u�����肵�悤�Ƃ����ł͖����ł��B
�@�J�o�[�����O�̃V�[�������𒍖ڂ��āA�悭�ł��Ă���Ύ~�߂Ăł��u���܂̃J�o�[�����O�悩��
���ȁv�ƖJ�߂܂��B �I��̓J�o�[�����O�̑�����ӎ����܂��B
�@
�@�ł��A�o���Ȃ��I�肪���܂��B
�@�J�o�[�����O���o���Ă��Ȃ���ʂł��~�߂܂��B
�܂��́A�~�߂Ȃ��Ő��ŕ\�����܂��B
�@�i�~�߂邱�Ƃ̓t���[�Y��������ƌ����܂��B�~�߂Ȃ��Ŏw�����邱�Ƃ��V���N���ƌ����܂��j
�g���[�j���O�Ɉڂ�܂��B
�@ �Q�Q�̍U��Ȃǂ����Ȃ���A�J�o�[�����O�̕��@�ɂ��ăg���[�j���O���܂��B
�|�W�V���j���O��R�~���j�P�[�V�����̎����A����D�揇�ʂł��ˁB
�@����ނ��̃��j���[���s���܂��B
�Ō�̃}�b�`�Ńg���[�j���O�̌��ʂ��m�F���܂��B
�@�g���[�j���O�̌��ʂ��o�āA�ŏ��̃}�b�`�ł͂ł��Ȃ������������̃}�b�`�łł���悤�ɂȂ邱
�Ƃ��ړI�ł��B
�@���̃��\�b�h�̌��ʂ̓R�[�`�̘r�����łȂ��A�I��́u�ӎ��v�ɂ��Ƃ��낪�傫���悤�ł��B
�@�}�b�`�ɂȂ�ƃ{�[���ɖ����ɂȂ��Ă��܂��āA�u�����ӎ����Ă��̂��v���|�[���ƖY��Ă��܂�
�I�肪�����܂��B �R�[�`���u�J�o�[�����O���悤�v�ƌ����Ă��A����{�[���ɂȂ�ƁA����ƃ{�[��
���������������A�������ǂ��������������Ă��邩�����Ă��Ȃ���������܂��B
�@���̃}�b�`�ʼn����ӎ����Ă�邩�B
�@���ꂪ���X�̗��K�ŏo���Ȃ��ƁA�����ł��u�ӎ������v���[�v���ł��܂���B
�@ �����A�R�[�`���^���Ă��ꂽ�e�[�}�A�����Ńg���C�������e�[�}���ӎ����Ȃ���Q�[�������悤�B��
�̐ςݏd�˂��u���E�ɉH�����P�W�v�ɂȂ�ƁA�R�[�`�͐M���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���b�c�g���C�I
�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə��� �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��]�v�Ə���
�ĊǗ��l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[���͂��܂��̂ł��̎w
���ɏ]���Ă��������B
|
|
|
|
|
|
�����T�@���E�̂P�W�̓��[���h�J�b�v��ڎw���Ă��� |
|
2008.11.10
�@��������߂���m�[�`�����X�I
�@���A���Z�T�b�J�[�I�茠���̊e�s���{����\�����X�ƌ��肵�Ă��܂��B
NABO�R�[�`�̃`�[���o�g�̑I����A����A�����s���̐ؕ�����ɂ��܂����B ���w����
��͉X�������т��c���܂���ł������A������߂鎖�Ȃ��A�l��{�̓w�͂��d�˂Ă�
�܂����B
�@�����A��x���Ƀ����j���O����p���悭�������̂ł��B
�@�T�b�J�[�̓`�[���Q�[���ł��B�������A�x���`�ɓ��邽�߂ɂ́A�[�b�P�������炤���߂�
�́A��l�œw�͂��鎖����ɂȂ��Ă��܂��B
�@���C�o���ɕ��������Ȃ��B�[�b�P�������炢�A���j�t�H�[���𒅂鎖��ڎw���Đl�m�ꂸ
�撣��p�B �K���������ʂ��ł�Ƃ͌���܂���B
�@�ł��A���̂悤�ȓw�͂𑱂��鎖���`�����X�����ގ��ɂȂ���܂��B ������߂���
�g���[�j���O�𑱂��Ă���A�����s���̐ؕ�����ɓ���Ƃ������ł��B
�@
�@�u������߂���m�[�`�����X�v �����A�Ȃ��Ȃ��X�^�����ɓ���Ȃ��A���M�����[�ɒ蒅����
���A�܂�Ȃ��Ȃ�܂��ˁB����Ȃɓw�͂��Ă���̂ɁB �݂�ȓw�͂����Ă���̂ŁA���K
�̎���ʂ̍��Ƃ�����߂Ȃ��Ƃ��������^���̋�������������ƌ�����ł��傤�B
�@�Ƃ���ŁA���Z�T�b�J�[�ł́A���Z�P�C�Q�N���ŏo�ꂵ�Ă���I������Ȃ�����܂���
�ˁB �ނ�́A�S�`�T�N�O�ɂ͏��w���ł����B ���w������ɂ͂ǂ�ȗ��K�����āA����g
�ɂ�������̂ł��傤���B
�@
�@�P�Ԗڂ́A�T�b�J�[��D�����N�ł��鎖�I �@�@�@
����́A���i���ȁH�D���łȂ���Α������܂���B
�@�Q�Ԗڂ́A�����������ł��鎖�I �@�@�@�@�@
�����̏������������łȂ��A���K�ł̃��t�e�B���O���������ł��u�����ĉ������v�Ƃ���
�C�����̐ςݏd�˂��A��ł��B�g�̂��Ԃ��Ȃ���{�[����D�������T�b�J�[�ł�
�u�����Ȃ��I�v�Ƃ����C�������G���W���ɂȂ�܂��B
�@�R�Ԗڂ́A�T�b�J�[�̖{���ƂȂ�v���[���o���Ă��邱�ƁB�@�@�@�@�@
�{���Ƃ́u�S�[����D���v�u�S�[�������v�����āu�{�[����D���v�u�{�[����D���Ȃ��v��
�������ł��B�@�@�@�@
�@�T�b�J�[�̓��[��������A�{�[���������X�|�[�c�ł�����A�����Ɂu�X�L���v�Ƃ������̂�
�K�v�ƂȂ�܂��B�@�@�@�@
�@�h���u�����t�F�C���g���p�X���A�����Ƒ���Ɩ������ӎ����ăg���[�j���O���鎖�ł�
�ˁB
�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
���X�g�����O�|�C���g���� ���Z�T�b�J�[�̘b�ɖ߂�܂��ˁB
�@NABO�R�[�`�̍D���ȃ`�[���̂ЂƂɁA��F���Z������܂��B
���N�O�Ɂu�Z�N�V�[�t�b�g�{�[���v�u�q�[���p�X����g�����ؗ�ȃp�X���[�N�v�őS�����
�Ȃ�܂����B ���̍��̑I��̓I�[�����ꌧ�o�g�ł��B�L���������Z�̑����́A���̓s
���{������̗D�G�ȑI�肪�W�܂�܂��B
�@����Ȓ��A�������Z�̖�F���Z�́A�����o�g�҂����̃`�[���ʼnh�����������܂�
���B�������A���̎��̑I��B�̕��ϐg���͂Ȃ�ƂP�U�T�Z���`�I�ł����B
�@�X�s�[�h�ƃL�b�N�͂ƃw�f�B���O�̍�����Ƃ���L���������Z�ɏ����߂ɂ́A��
�l�Z��������܂���B
�@������O�ꂵ���l�Z�ŁA���x�ȃh���u���ƃV���[�g�p�X����̂Ƃ����T�b�J�[�Ń{�[��
�������܂����B �u������߂���m�[�`�����X�v ���́A���̌��t�́A��F�̎R�{�ē�
���t�ł��B
�@��F���Z�̑I��B�́A���Z���ɂȂ��Ă���Z�p��g�ɂ����̂ł͂Ȃ��A���w�Z�`��
�w�Z��т��č��x�ȃ{�[�������̃g���[�j���O�����Ă������ʂ��Ƃ������ł��B
�@ �{�[�������͂P�`�Q�N�ł͐g�ɂ��܂���B ��F�s�̃`�[���́A���N�T�b�J�[�̑S
�����ɂ��o�ꂵ�Ă��܂��B
�@�������ۂɌ��܂������A�X�L���t���ȏ��N�B�ł����B ���������A�w�������A���m�ȃ���
�O�p�X���R���B
�@���̂悤�ȃX�g�����O�|�C���g�������Z���������ŁA��F���Z�̃X�g�����O�|�C���g��
�u�Z�p�v�ł����B �w�������Ȃ��A���������Ȃ��I��B���u�Z�p�v�Łu�́v�����Ƃ�������
�����������̂ł��B
�@����́A���{��\�Ɛ��E�̋����e���̊W�Ɏ��Ă��܂��H �̊i�ɂ͗�邯��
�ǁA���m�ȋZ�p�ƖL�x�ȉ^���ʁA�����Ĕ��f�͂�Ђ�߂��̂���T�b�J�[�Ő��E�Ɛ키�B
�@���N�T�b�J�[�ł��A�u�p�[�t�F�N�g�X�L���v�ƂƂ��Ɂu�����܂����v��u�n�[�h���[�N�v��g�ɂ�
���鎖���ۑ�Ƃ��āA�e�g���Z���ł��ϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B
�@�T�b�J�[���N���T�b�J�[�I��ɂȂ�B�̂ł͂Ȃ��A�T�b�J�[�I��̏��N�������T�b�J�[
���N���Ƃ����l�����������āA�����̏��������͑������ǂ��A�����Ɂu�v����������
�����Ă����B���ꂪ��ł��B
�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�����E�̂P�W�̓��[���h�J�b�v��ڎw���Ă���
�@���Z�T�b�J�[�őS�����ɏo�Ē��ڂ���AJ���[�O���琺��������B �ЂƂ̖������m
��܂���B �ł��A�}���`�F�X�^�[�t��A�`�b�~�����A��o���T�Ȃǂ̃r�b�O�N���u���琺��
���������炷�������ł���ˁB ����ȃr�b�O�Ȗ��������ăT�b�J�[�����ė~�����Ǝv����
���B
�@���Z���Ƃ����P�W�B
�@���b�V�͂P�W�Ń��[���h�J�b�v�ɏo�ăv���[���Ă��܂����B
�@���E���̂P�V��P�W�́A���[���h�J�b�v�ɏo�ăr�b�O�N���u���琺��������̂�_��
�Ă��܂��B �S���̃T�b�J�[���N���A2014�N�u���W������2018�N����ڎw���Ċ撣��
�ė~�����ł��ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W���j�A�T�b�J�[�R�[�`�@�m�`�a�n
�@�@�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K�� �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��
�]�v�Ə����ĊǗ��l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[����
���܂��̂ł��̎w���ɏ]���Ă��������B
|
|
|
|
|
|
�����S�@�t�@�[�X�g�^�b�`�ő�������킻�� |
|
�@�Q�O�O�W�D�P�P�D�R
�@�`�t�@�[�X�g�^�b�`�ő�������킻���`
�@�P���̃t�F�C���g��t�e�B���O�o�C�u�����g���C���Đg�ɂ��Ă����B �W���K�X�e�b�v��
�ł���悤�ɂȂ������A �V�U�[�X���_�u���ōs����悤�ɂȂ����B
�@ �߂����t�@���^�W�X�^���X�e�[�W�V����W�A�W����P�O�ƃX�e�b�v���Ă����B
�{�[���R���g���[���̓o�b�`�����I
����́A�f���炵���I
���Ⴓ�����������Ŋ��悤�B
�@���������N�����ɃA�h�o�C�X������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�{�[�����ꔭ�ŃR���g���[���ł���Ȃ�A�����ł͂ǂ̏�ʂŎg���̂����ʓI����
���B
�@�����^�b�`�ŃR���g���[������Ƃ������Ƃ͎��̂悤�ȏ�ʂ�z�����Ă݂Ă��������B
�@ ����`�[���̃N���A�{�[�������ڂ�Ď����̂ق��֗��������B �悵�A�{�[���̗����_
�ɑ��肱�����B
�@ �����܂ł�OK�ł���ˁB
�@���R����DF���{�[���̗����_�Ɋ���ė��܂��B
�@�ꏊ�́A�y�i���e�B�G���A�ƃn�[�t�E�F�C���C���̊Ԃ��炢�ł��B
�����ŁA�u���f�v�Ɓu�t�@�[�X�g�^�b�`�̎��v�̍����o�܂��B
�@�`�N�́A�u�܂��A�{�[�����L�[�v���āA��������킵�ăA�V�X�g���S�[����_�����v�Ƃ��āA
�{�[�����������Ȃ���A�����_�ɑ��肱�݂܂��B
�@�a�N�́A�u�{�[���̗����_�ɂ͎�������ɓ��ꂻ�����A�ł����ʂ��瑊��������Ă���
����B���ɃX�y�[�X�����邩��A�t�@�[�X�g�^�b�`�ŃX�y�[�X�ɉ^��ł݂悤�v�Ƃ��āA�{�[
���Ƒ���ƃX�y�[�X�����Ȃ���A�����_�ɑ��肱�݂܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�T�b�J�[�̓_�C�i�~�b�N�ȃX�|�[�c�ł��B
�@�����v���[�A�����v���[���r��邱�ƂȂ��Ȃ����Ă����܂��B
�`�N�̓e�N�j�b�N�͂���܂����A�ςĔ��f����Ƃ����ӎ�������Ȃ��悤�ł��B�{�[����
�����̃��m�ɂł��Ă��A����S�[���̑O�ł͌������v���b�V���[���āA�V���[�g��A�V
�X�g�܂Ŏ����čs���Ȃ���������܂���B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�a�N���`�N�Ɠ������炢�̃e�N�j�b�N������܂����A�{�[�������łȂ������X�y�[�X��
�Ŋς邱�Ƃ��ł��܂��B�������L�[�v���邱�Ƃ����A����Ɏ���Ȃ��Ƃ���փ{�[����
�^�ԂƂ����ӎ������邽�߁A�t�@�[�X�g�^�b�`�Ń{�[�����X�y�[�X�ɉ^�яo�����u�ԂɁA
����f�t�F���_�[���ЂƂ肩�킷���Ƃ��ł��܂����B
�@���I�D�ʂ���u�̃{�[���^�b�`�ō�邱�Ƃ��ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@ �@
�@���̍��͑傫���ł��ˁB �t�@�[�X�g�^�b�`�Ń{�[�����^�Ԏ��̑���ł��B���̃v���[
�����₷���ꏊ�։^�Ԃ����łȂ��A����̎��Ȃ��Ƃ���A�傫���o���R���g���[���B����
��̋Z�p�Ɣ��f���A�����āA�f���炵���v���[���ł���Ƃ������ł��B
�@ �{�[������������G�邱�Ƃ��ł���I��ɂȂ�����A���������̃^�b�`�ŋǖʂ��
����I���ڎw���Ă��������B
�@�삯�����̔��f�ƃ{�[���R���g���[���̃e�N�j�b�N�ł��B �`���̃}���h�[�i�̂T�l����
���P��̃^�b�`�̐��m���̘A���Ő��܂�Ă��܂��B
�@���O���疳���Ƃ��A�o���Ȃ��ƌ���Ȃ��ŁA���b�c�g���C�I�����Ƃł��邼�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �W���j�A�T�b�J�[�R�[�`�@�m�`�a�n
�@�@�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K�� �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕��͌����Ɂu�����}�K��
�]�v�Ə����ĊǗ��l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[����
���܂��̂ł��̎w���ɏ]���Ă��������B
|
|
|
|
|
|
�����R�@�@�U�N���őI���i�g���Z���j�ɑI�ꂽ���Ƃ��l���ł����H |
|
�@�@�@�@�@�Q�O�O�W�C�P�O�C�Q�U
�@�@�`�U�N���őI���ɑI�ꂽ���Ƃ��l���ł����H �`
�@�@�@���g���Z���͂S�N������n�܂�܂��B
�@�����̓s���{���ł̓g���Z���͂S�N������n�܂�܂��B
�@�����`�[���̐��E�Œn��g���Z���Ŋ����J�n����܂��B �s���{���̂S�N���g���Z���A
������U10�g���Z���͂S�N���̂����ɑI������܂��B �قƂ�ǂ̏ꍇ�A�T�N���g���Z��
�����̃����o�[�P���鎖�������悤�ł��B
�@�Ƃ������Ƃ́E�E�E
�i�P�j�S�N���őI��Ȃ���`�����X���Ȃ��̂��H
�@ �������A���Ƃ��S�N���őI��Ȃ��Ă��AU11�i�T�N���j�AU12�i�U�N���j�őI�ђ����̂�
��ʓI�ł��B �t�Ɍ����ƁA�����AU12�i�U�N���j�ɂȂ������ɂ�����ł���I���I�l��
���邩�Ƃ��������ۑ�ɂȂ�܂��B
�@ �S�N���őI���ɑI��ł��A�V��ɂȂ��āi�܂�A�I�ꂽ���ɖ������āA�g���[�j��
�O��ӂ鎖�j���܂�����A�z�b�Ƃ��Ă��܂��i�܂�A����I�ꂽ����A5�N���A�U�N
���ƑI�ꑱ���邾�낤�j�Ƃ����P�[�X������܂��B ���w���̂P�N�Ԃ͑�l�̊��o�ł�
���A�R�N���̑�������Ǝv���܂��B ���Ƃ��I��Ȃ��Ă��A���N�ԁA�e�[�}���i�����g
���[�j���O������A�N���u�̃R�[�`�̖ڂɂƂ܂鎖���\�����蓾�܂��B �܂��A���̂悤
�Ȑ������A�s�[������K�v�����邩���m��܂���B
�@�i�Q�j�S�N���őI��邽�߂ɂ͂ǂ���������̂��H
�@�R�N���܂ł̃g���[�j���O���d�v�ɂȂ�܂��B�S�N���őI��邽�߂̋Z�p�Ȃǂ��g
�ɂ��Ă��邩�ǂ����ł��B
�@���͎��̓��e�͐g�ɂ��ė~�����ƍl���Ă��܂��B�܂��A�g�ɂ��Ă��Ȃ��ƂS�N��
�ł̐L�т����҂ł��Ȃ������m��܂���B �@�@
�@�@�@
�@�@�@�@�P�D10�����x�̃L�b�N�𐳊m�ɂł��邱�ƁB�@�@
�@�@�@�@�Q�D�L�b�N�̓C���X�e�b�v�A�C���t�����g�A�C���T�C�h���R�蕪�����邱�ƁB�@
�@�@�@�@�R�D�h���u���ł̓A�E�g�T�C�h���g�����h���u�����ł��邱�ƁB�܂��A�C���T�C�h�A
�@�@�@�@�@�@�@�A�E�g�T�C�h�ł̐�Ԃ��������łł��邱�ƁB�@�@
�@�@�@�@�S�D�^�[�����ł��邱�ƁB�C���T�C�h�t�b�N�A�A�E�g�T�C�h�t�b�N�A�\�[�����g���A
�@�@�@�@�@�@�@�N���C�t�^�[�����o����A�Ȃǂł��B�@�@
�@�@�@�@�T�D�w�f�B���O�̊�b���ł��Ă��邱�ƁB�@�@
�@�@�@�@�U�D�����Ђ��̃Z���X��g�ɂ��Ă��鎖�B�܂�A�{�[���R���g���[�������ŏI
�@�@�@�@�@�@�@���̂ł͂Ȃ��A����Ƃ̂����Ђ����ӎ����Ȃ���A�t�@�[�X�g�^�b�`�A�h���u
�@�@�@�@�@�@�@���A�t�F�C���g�A�����E�B�Y�U�{�[���Ȃǂ��ł��邱�ƁB�@�@
�@�@�@�@�V�D�U��ɂ킽���āu�n�[�h���[�N�v���ł��邱�ƁB�@
�@�����U12�ŗv�������t�@�N�^�[�ł����A�U�N���ɂȂ��ēˑR�g�ɕt�����̂ł͂Ȃ��A
�S�N���̎��ɁA���̊�b�������Ă��邱�ƂŁA�T�A�U�N���ł̃n�[�h���[�N�̓y������
�����ł��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@���R�N���̂����ɑ̌����Ăق�������
�@
�@ �S�N���ł�����x�̃X�L����g�ɂ��邽�߂ɂ́A�R�N���ł��łɍ��x�Ƃ�������g
���[�j���O������K�v�����邩�̂悤�Ȋ��o���܂��B �ł��A�R�N���ɂ͂R�N���Ƃ�
�đ̌����ė~������������܂��B
�@����́A�u�c�q�T�b�J�[�v�ł��B
�@ �{�[���ɐG�肽���A�{�[���ɐG�肽���B ����̃{�[���������̃{�[���������̂���
�ɂ������B ���̂��߂ɂ̓{�[���ɌQ���鑊��□�������܂��Ȃ��A�̂̐ڐG����������
�Ȃ��A�c�q�ɔ�э��ޑ̌����K�v�ł��B ���̌o����������x�̊��ԑ̌����邱�Ƃɂ�
���āA�u�R���^�N�g�X�L���v�̏K���ɍ������Ă��܂��B
�@ �u�̂����Ɏg���v�u�̂̓�����v ���̓y��͂R�N���ł́u�c�q�T�b�J�[�v�ŁA��������
��������A�Ԃ�������Ƃ��������u�T�b�J�[�ł͓�����O�v�Ƃ������o��g�ɂ��Ăق�
���̂ł��B
�@ �R�N���ł���A�u�{�[���������̂��̂ɂ��悤�I�v�Ƃ������������ŁA�{�[���ɑ�
�鎷���S���g�ɂ��Ă����ł��傤�B ����ɁA�u������{�[��������Ȃ��悤�ɂ��悤�v��
�������������ŁA�W�c�̒��Ń{�[���������Ă��Ă��A����邾���Ȃ̂ŁA�W�c�̊O��
�X�y�[�X�Ƀ{�[���������Ă������B
�@���������ӎ��ł̃h���u�������܂�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@����ȏ��w�R�C�S�N���̎���
�@
�@�@�������čl����ƁAU12�̃T�b�J�[��U10�Ō��܂�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���BU10
�Ŋ�b�����߂����邽�߂ɂ́A3�N���ɉ�������ׂ����A�Ƃ����ۑ肪���܂�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@����N��ɑ��Ă��X�L�����v������Ă��܂��B
�@�@�R�N���ŃX�L����g�ɂ��邽�߂ɂ́B���̑O�ɉ�������������B �@
�@�@�@�@�@�P�D�T�b�J�[�̓������ł��邽�߂̃R�[�f�B�l�[�V���� �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����́A�T�b�J�[�̕��G�ȓ��������邽�߂ɂ́A�T�b�J�[�̃~�j�Q�[����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ł͐g�ɂ��邱�Ƃ�����̂ŁA�u�R�[�f�B�l�[�V�����g���[�j���O�v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���āA�{�[�����K�⑊�肠��̗��K�ł��̂����Ɏg���y�����邱
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃł��B �@
�@�@�@�@�@�Q�D�S���������������Ă݂܂��@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r�u�X�����̂�����ɋ���ŁA���݂��̃r�u�X����荇���B�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������u�����ۃg���v�̃g���[�j���O�B �@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̗V�ъ��o�̃g���[�j���O�ŁA�g�ɕt�����Ƃ�����܂��B �@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�j�U�߂ɏo��C�����@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�j�w��̋C�z��������邱�Ɓ@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�R�j�r�u�X�����ꂸ�ɑ���̃r�u�X�����A�����Ђ��@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�S�j�A�����āA�r�u�X�����ɍs���u�ϋɓI�Ȏp���v�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�T�j�Ƃ��ĉ������A�Ƃ��Ċ������Ƃ������������Ɛ����̌��@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�U�j�������Ă����āA�S�̋��ꏊ�f���āA�����Ђ�����B �@
�@�@�@�@�@�R�D���肪�����Ԃł����Ȃ���Ԃł��Q�ĂȂ��Ńv���[�ł���B
�@�@�@�@ �@�@�@�@����͓����������܂��A���M�����Ă��Ă͂��߂� �u�����Ђ��v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ł���Ǝv���܂��B�X�L���̑����́u�����Ђ��Ɏg�����́v�Ƃ����y��@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƁA�T�b�J�[�ł̓{�[���������Ă���Ƒ��肪�K�����ɗ���X�|�[�c��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂ŁA����Ȃ����ɂ́A�h���u���̃X�L�������ƂƁA�����ς�\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��g�ɂ��邵������܂���B �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A���肪�߂Â��Ă���̂�������O�ŁA���̑���Ƃ����Ђ����邱
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��T�b�J�[���Ƃ������ɋC�����ė~�������̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@���������ƃ��[�j���O�𑱂��悤 �@
�@�uJFA�`�������W�Q�[���@�߂����t�@���^�W�X�^�v
�@�@http://www.jfa-challengegame.com/index2.html�@
�@�@�{������ɍs����DVD�t���u�b�N�������Ă��܂��B
�@�@http://tinyurl.com/48cm34
�@�@�������A�y�����ƃP���̃W���K�A�t�F�C���g�A���t�e�B���O����K���̌N�����Ȃ�
�A�{�[���R���g���[���Ɏ��M������Ǝv���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@
�@
�@�@�@�@���X�L���t���ȂS�N���ɂȂ邽�߂�
�@�P�N���`�R�N���܂ŁA�u�T�b�J�[�͊y�����v�Ɗ��������Ȃ���A�u�T�b�J�[�͊y�����A��
�ǁA�L�r�V�C�v ���̗��ʂ����܂��w�����Ă��������K�p�ł��B �u�n�[�h���[�N�v��g�ɂ�
�邽�߂̓y��Ƃ��Ă��d�v�ł��B ���葱����ΐh���A�ł��A�{�[����D�����炱������
���m�I �������������^���ʂ̓y��́A�R�N���ȉ��ł��w�����邱�Ƃ��\�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@ ��U�P�O�g���Z���ł́H
�@�@�{�[�������̋Z�p�łȂ��A����̋t���Ƃ�Z�p���K�v�ł��B �����̗��K����u����
�������v�g���[�j���O�����邱�ƁB����̃v���X���������Ă������ƁB ����ŁA��
�̑O�̂P�l���炢�͊ȒP�ɂ��킹��X�L����g�ɂ��ė~�����Ƃ���ł��B
�@�K���ʂ⎩�o���Ȃǂ́A�T�C�U�N���ł��g�ɕt���܂��B
�@���Ɍ���������K�v�͂Ȃ��ƍl���܂��B ��������u���ȊǗ��v�̊�b�Â��肪���
���B
�@�����ŗp��������ł��邱�ƁA�R�[�`�̘b���āA����ŁA���ۂɍs�����N������
���B
�@�y��ł���X�^�[�g���C����U�P�O����ł����A�悢�y��A�悢�X�^�[�g��邽�߂�
�́AU9�ȉ��Ŏ��̂悢�g���[�j���O���s�����Ƃ��K�v�ł��B
�@���̓��e���N���u�̃R�[�`���畷���Ă���I��͖�肠��܂��A�u���߂ĕ����v�A��
�����ꍇ�́A���ԂŃg���Z���Ɍ����Ă���q��������A�������畷���o���邭�炢�̐�
�ɐ����ق����ł��ˁB����́A�q�����m����邱�Ƃł��B�e������́A�����ƌ�����Ă�
�������B
�@�@�@�@�Ǘ��l�₶�܂͂m�n�a�n����̃��[���}�K�W���ƃv���O���������Ă��܂��B
 �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕������Ɂu�����}�K�� �@�m�`�a�n����̓��[���}�K�W���s���Ă��܂��B����]�̕������Ɂu�����}�K��
�]�v�Ə����ĊǗ��l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B��قǁA�m�`�a�n���烁�[��
�͂��܂��̂ł��̎w���ɏ]���Ă��������B
|
|
|
|
|
|
�����Q�@�uJFA�`�������W�Q�[���@�߂����t�@���^�W�X�^�v���������ł����H |
|
�@�@�@�@�Q�O�O�W�C�P�O�C�P�W�@
�@�@�@���͂��߂�
�@�uJFA�`�������W�Q�[���@�߂����t�@���^�W�X�^�v�Ƃ́A��N����X�^�[�g����JFA�̃v���O
�����ł��B
�@�����Ȃ�i�e�`�̐�`�H�ƌ���ꂻ���ł����A�������Ⴀ��܂���B��̓I�ɂ͎��̃y�[
�W�������ɂȂ�Ƃ킩��₷���ł���B
�@������ɂ��킵�����e���łĂ��܂��B
http://www.jfa-challengegame.com/index2.html
�@�{������ɍs����DVD�t���u�b�N�������Ă��܂��B
�@�@�@�@����������������n�߂悤
�@�߂����t�@���^�W�X�^�͂t�W�ȏ�A�܂�A���w�Q�N���ȏォ��̓��e�ł��B�߂����N��
�b�L�͂t�W�ȉ��A�܂�A���w�Q�N�������̓��e�ł��B
�@���̃v���W�F�N�g�̑_���́A�ӂ�����܂��B
�@�ЂƂ́A�O�V�т����Ȃ��Ȃ�������ł́A���w�Z�ɏオ��܂ł̃L�b�Y�N��ŗV�т�
�Ȃ��Őg�ɂ���ׂ��^���\�͂��A�T�b�J�[�I�ȗV�т̂Ȃ��ŁA�u�v��I�Ɂv�g�ɂ���
�������Ƃ������̂ł��B
�@�v�������鎖������܂��B�V�C�̂悢���j���ɁA����Ńe���r�Q�[�����Ă�����A
�^���\�͈͂炿�܂����ˁB
�@�O�V�т����Ȃ��Ȃ������́A�ꏊ�����Ȃ��Ȃ��������������܂����ǂˁB
�@�@�@�@���P���͎�������[�h���Ă���
�@�����ЂƂ́A��͂�A���{�l�̓{�[���R���g���[������������g�ɂ��ė~�����Ƃ���
�ړI�ł��B
�@�̊i�ɗ����{�l�͓�Čn�̃T�b�J�[�i�P���̂悤�Ɂj�v���X�A�����āA�����đg�D�v��
�[��W�J����T�b�J�[�������Ă��鎖�̓I�V������̎��ォ�猾���Ă��鎖�ł��B
�{�[�������Ƃ������t�e�B���O�ł��B�P���̓��t�e�B���O�̑���𐢊E�I�Ȏ��삩��
���Ă�����Ƃ������ŁA���{�����щ���Ă�����ł��ˁB
�@���{�T�b�J�[�̒�ӂ�������j�Ƃ�����ł��傤�B�i�p�`�p�`�j
���̂߂����t�@���^�W�X�^�ł́A���t�e�B���O�̂ق��ɂ��A�h���u���A�^�[���A�t�F�C���g�̂�
���グ�Ă��܂��B
�@����ɉ����A��Ń{�[�����������Ƃ����܂��B����Ă݂�Ɩʔ����ł���B���ЁA�e�q��
����Ă݂Ă��������B
�@����́A�u�R�[�f�B�l�[�V�����g���[�j���O�v�ƌĂ����̂ŁA�킩��₷�������A�u�g
�̂��Ȃ��v�̃g���[�j���O�ł��B
�@���̃R�[�f�B�l�[�V�����\�͂́A�����������ɐg�ɂ��₷���ƌ����Ă��܂��B�Ԃ���
��ł��A���Ă�悤�ɂȂ�����n�߂��郁�j���[�����邭�炢�ł��B
�@���́A�R�[�f�B�l�[�V�����\�͂�g�ɂ��Ă����āA���w�Q�N�����炢����{�[��������
���{�i�I�ȃT�b�J�[�̃g���[�j���O�ɓ����Ă������ŁA�����悭��B���ł���Ƃ����d�g
�݂ł��B
�@��������w�R�N�����炢���瓯���Ɏn�߂�Ƃǂ��Ȃ�ł��傤���B
���t�e�B���O���̂��̂��̂̃o�����X�������K�ɂ��Ȃ�̂ł����A�o�����X�����Ȃ�
�̂ł͂Ȃ��Ȃ���B���Â炢���̂ł��B
�@���́u�߂����t�@���^�W�X�^�v�̓����́A�̂̑S���ϓI�Ɏg���Ƃ������ł��B���E��
���A��A����S�������܂��B
�@�����āA��B��ɂ���āu���v������Ă��܂��B�V������X�^�[�g���ĂQ�O���܂ł����
���B
�@�Q�O���̓P���������璩�ёO�ł����A����ł���B�ł��A��ы��Ȃ��ŁA�X�e�b�v�A�b�v
����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B
�@���Ȃ݂ɂV���͔��o�b�W�ł��B�Q�O���͋��o�b�W�ł��B���莎������ƃo�b�W������
����d�g�݂ł��B�m�`�a�n�R�[�`�̃`�[����g���Z���ł��A�S�����u�߂����t�@���^�W�X�^�v
�̖{���Ăc�u�c�����Ȃ�����K���Ă��܂��B
�@�N�ɉ����������܂��B���͌��莑�i�������Ă��܂��B
�@�F����̃`�[���ł��A����\�������āA���������Ɗy�����Ǝv���܂��B�蒠�����炦
��̂ŁA�v��I�Ɏ��g�߂܂��B
�@���܂��ɁA�����Ƃ�ƃT�b�J�[����̐�قǂ̃z�[���y�[�W�ɖ��O���ڂ��Ă��炦��
���B�L���ɂȂ�����ǂ����悤�B�i���[�O����U���邩������Ȃ����B
�@�@�@�@�@�������������ɂȂ낤�A���ł��P�Ԃ�ڎw����
�@�m�`�a�n�R�[�`�̃`�[���ł́A���N���猟�����n�߂Ă��܂����A����Ȃ��Ƃ�����܂�
���B
�@���o�b�W�̂V���ɂȂ��Ȃ����i�ł��Ȃ��q�����܂����B
�����ł͊���̂ł����A�����Ń{�[�����������グ��Ƃ����e�X�g���o���Ȃ��ĂȂ�
�Ȃ����i�ł��܂���ł����B
�@�ł��A�������g����悤�ɗ��K�����������ŁA���͒��w���̃N���u�`�[���Ŋ��Ă�
�܂��B���܂ɍ����ł��V���[�g���邻���ł��B�Â��Ȃ�܂ŁA���������ɂȂ�Ȃ���ꐶ��
�����K���Ă����p���v���o���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@����������
�@�߂����t�@���^�W�X�^�͑S���̏��X���A�}�]���ő��������ōw���ł��܂��B
http://tinyurl.com/48cm34
�@�P���̃��t�e�B���O��W���K��t�F�C���g�̃r�f�I�����ė��K���Ă���N�����Ȃ�A�u����
�J���^���I�v�Ƃ������j���[������̂ŁA�Q�O���ڎw���Ċ撣�낤�I
�@�R�c�́A�u�o���Ȃ����Č���Ȃ��v���I
�܂��ˁ@���b�c�g���C�I
|
|
|
|
|
|
�����P�@�����t�́@���b�c�g���C�ł��B�~�X�����ꂸ�A�܂�����Ă݂܂��傤 �@ |
|
�@�@�@�@�@�Q�O�O�W�C�P�O�C�P�P
�@�@�͂��߂܂��ā@NABO�@�ł��B
�@���́A�ǂ��ɂł����鏬���ȃ`�[���̃R�[�`�ł��B
�@�L���ȃ`�[���̃R�[�`�̓Z���N�V������ʉ߂����I�肵������ɂ��܂���B
�@���v���̑I��͖{���o���܂����A���N�T�b�J�[�̌���̐��͒m��܂����ˁB
�@������A�o���Ȃ��q���������o����悤�ɓ��X�w�͂��Ă��錻��̐��ɂ͑Ή��ł�
�܂���B
�@�s���{���̃g���Z���R�[�`�B���A�m���Ă��邯�ǖ{�ɏ�������A�����}�K��|�[�g��
���M���悤�Ƃ���l�͂قƂ�ǂ��܂���B
�@�g���Z���ɍs���Ă���q�͒m���Ă��Ă��A�����ĂȂ��q�͒m��Ȃ��B����ł����̂ł�
�傤���H�B
�@�����ŁA�������̋^��⌄�Ԃ߂邽�߂ɁA����������Ƃ������܂��B
�@���͒n��ƌ��̃g���Z���R�[�`�����Ă��܂����A�M�S�ɃR�[�`���O���Ă���Ă���R�[
�`�B�ɂ͖{���ɓ���������܂����A�����q�������ɓ`�������̂��A�q�������͉�����
���~�߂����^��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�@ �T�b�J�[�̓R�[�`�����Ȃ��Ə�B���܂���B�ł��A�ی�҂��������������R�[
�`�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�T�b�J�[���N���������ی�҂�T�b�J�[�R�[�`���S�҂��m���Ă��đ��͂���܂�
��B
�@�ی�҂̓R�[�`�Ɠ������炢�q�������ւ̉e���͂�����܂��B�܂�A�T�b�J�[����
�B��������Ήƒ납��A�Ƃ������ł��B
�@�n�߂鎞�Ɂu�x������v���͂���܂���B������ł��\���Ԃɍ����܂��B�����܂�
�傤�B
�@�����t�́@���b�c�g���C�ł��B�~�X�����ꂸ�A�܂�����Ă݂܂��傤 �@�@�@�@
�@�������A��p�v���O���\�z���E�E�E�B
��������A���y���݁E�E�E�B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���N�T�b�J�[�R�[�`�@NABO
�@�@�@���łɂT�Q�l�̕��������}�K�ɍw�ǂ���܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
�@�@ �@���[���}�K�W���s���܂�����]�̕������Ɂu�����}�K��]�Ə����āv�͊� �@���[���}�K�W���s���܂�����]�̕������Ɂu�����}�K��]�Ə����āv�͊�
���l�́u�₶�܁v�܂����[�����Ă��������B
�@�@ �ȉ��͂m�`�a�n����̏Љ�ł��B
�@�n�����͎��̂悤�ȓ��e�ɂȂ�܂��B
�@�Ȃ��A����A���[���}�K�W���o�^�������ɁA�����Ń��|�[�g�������グ�邻���ł��B
�^�C�g���́u���N�T�b�J�[�A�X�T�Ԃŏ�B������K�@�v �����T�b�J�[�R�[�`�����ʂ��o
���Ă�����K���@�ł��B�����ł��̂ł��Гǂ�ł݂Ă��������B
�@�Ȃ��A��NABO�R�[�`�́A�P����}�b�V�[�̗F�l�ł��B
�@���t�e�B���O��h���u���̑�����悭�m���Ă��܂��B����܂ŁA�N�������Ă���Ȃ���
���T�b�J�[��B�@��T�b�J�[�Ŋ��邽�߂̃R�c�Ȃǂ��o�������ł��܂����B�P
����}�b�V�[�̃e�N�j�b�N�ƍ��킹�āA�T�b�J�[���N�̂�������A���ꂳ��A�����ăT�b
�J�[�R�[�`���S�҂ɂ����߂̃����}�K�Ɩ������|�[�g�ł��B���ЁA�\������ł�������
�ˁB�@�@�@�@ |
|
|
|
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@
�@�@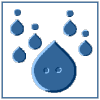
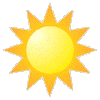
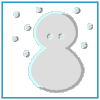
 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@�@�@�@
�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@

